税金に関するお役立ち情報
仮想通貨を少しずつ利確すると税金はどうなる?節税のコツも解説
最近、持っている仮想通貨の価格が上がってきたから、少しずつ売って利益を確定したいな。こまめに売れば、一回の利益が小さいから税金も安くなるって聞いたんだけど、本当かな?🤔
そのお考え、よく分かります。利益が出ていると嬉しい反面、税金のことが気になりますよね。ただ、「少しずつ利確すれば税金が安くなる」という点については、実は少し注意が必要です。今日はその仕組みと、賢い税金対策について詳しく解説していきますね!
■ 「分割利確」しても税額は変わらない?仮想通貨の税金の基本
まず最も重要なポイントからお伝えします。仮想通貨の税金は、一回の取引ごとではなく、1月1日から12月31日までの1年間の利益(所得)を合計して計算されます。そのため、一気に100万円の利益を確定しても、10万円の利益確定を10回繰り返しても、年間の利益が同じ100万円であれば、最終的に納める税額は原則として同じになります。
仮想通貨の利益は、原則として「雑所得」に分類され、給与など他の所得と合算して税額が決まる「総合課税」の対象となります。総合課税は、所得が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用されるのが特徴です。
出典: 国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※上記に加えて、別途住民税が約10%かかります。
■ 少しずつ利確する際の本当のメリットと注意点
税額が変わらないなら、少しずつ利確する意味はないのでしょうか?いえ、そんなことはありません。分割して利確することには、以下のようなメリットと、それに伴う注意点があります。
-
メリット:税金額を下げる
仮想通貨の税金は上述の通り総合課税を採用しているために、利益が多ければ多いほど税率が上がる仕組みになっています。年度ごとに少しづつ利確することで、その年度の利益を下げ、税率を下げる効果があります。 -
注意点:仮想通貨の時価が変動しやすい
一度に全部利確するのではなく、年度ごとに少しずつ利確することで、税金を下げるメリットがある反面、仮想通貨は非常にボラティリティ(価値の変動)が激しい資産です。そのために、想定していた利益が年ごとに安定して計上できないという注意点があります。
■ 賢く付き合うための3つの節税・申告テクニック
税金の仕組みを理解した上で、少しでも負担を抑えるために知っておきたいポイントを3つご紹介します。
-
1. 年間利益20万円の非課税枠を意識する
給与所得者など一定の条件を満たす場合、仮想通貨を含む雑所得の年間合計が20万円以下であれば、確定申告が不要になります。この枠を意識して、年内の利確金額をコントロールするのも一つの戦略です。 -
2. 年をまたいで利確タイミングを分散する
例えば、年末に大きな利益が出ている場合、その一部を年内に利確し、残りを翌年以降に利確することで、単年での所得が急増するのを防ぎ、適用される税率を抑えられる可能性があります。 -
3. 経費を漏れなく計上する
仮想通貨の利益を得るために直接必要だった費用は、経費として利益から差し引くことができます。例えば、取引所の手数料、送金手数料、税金計算ツールの利用料、関連書籍の購入費などが対象です。忘れずに計上しましょう。
なるほど!年間の合計利益で考えるんですね。取引回数が増えると、計算がすごく大変そう…。何か良い方法はないんですか?🤔
おっしゃる通り、手計算は非常に困難です。そこで役立つのが損益計算ツールです。取引所の取引履歴(APIやCSVファイル)をアップロードするだけで、年間の損益を自動で計算してくれます。計算ミスを防ぎ、確定申告の手間を大幅に削減できるので、仮想通貨投資家にとって必須のアイテムと言えるでしょう。
💡 今日のまとめ
- 仮想通貨の税金は、一回ごとの利益ではなく「年間の合計利益」で計算されるため、分割して利確しても合計額が同じなら税額は変わりません。
- 給与所得者などの場合、年間の雑所得が20万円以下なら確定申告は不要です。これを意識した計画的な利確が有効です。
- 取引回数が増えると計算が複雑になるため、損益計算ツールを活用して、正確かつ効率的に損益を管理することが賢明です。

この記事の監修者
村上 裕一(公認会計士・税理士)
公認会計士試験合格後、大手監査法人、メーカー経理財務、会計事務所を経て独立開業。仮想通貨・NFT・ブロックチェーンゲームを専門とする税理士として活躍。自らもSTEPNなどのブロックチェーンゲームなどをプレイし、多くの投資家の税務を支援している。
>> ホームページはこちら
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
免責事項
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
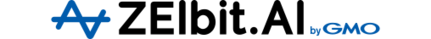

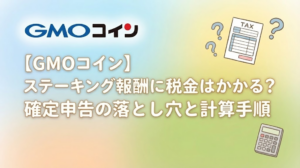


コメント 0件