仮想通貨にかかる税金、高すぎる?日本の仮想通貨税制と今後の見通し【2025年最新版】
※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
■ なぜ仮想通貨の税金は高いのか?「雑所得」と「総合課税」の仕組み
日本において、仮想通貨の売買や交換によって得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。そして、給与所得や事業所得など、他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となります。
この仕組みが、税金が高くなる主な理由です。所得の合計額が大きくなるほど、より高い税率が適用される「累進課税」が採用されているためです。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率(一律) | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 10% | 20% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 10% | 30% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 10% | 33% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 10% | 50% |
| 4,000万円超 | 45% | 10% | 最大55% |
例えば、給与所得が500万円の人が仮想通貨で500万円の利益を得た場合、合計所得1,000万円に対して税金が計算されます。その結果、所得税と住民税を合わせると、利益の40%以上が税金として徴収される可能性も十分にあります。
出典: 国税庁 No.2260 所得税の税率■ 税金が高すぎると言われる2つの理由|損失繰越・損益通算ができない
税率の高さに加えて、株式投資やFX(外国為替証拠金取引)では認められている有利な制度が、仮想通貨には適用されない点も大きな課題です。
- 損失の繰越控除が「ない」
ある年に大きな損失が出ても、その損失を翌年以降の利益と相殺することができません。つまり、年をまたぐと損失は切り捨てられてしまいます。 - 損益通算が「ない」
仮想通貨取引で出た損失を、株式投資の利益や給与所得など、他の所得と相殺(損益通算)することができません。「雑所得」の中でも一部の所得とは通算可能ですが、範囲が非常に限定的です。
これらの制約により、特に相場変動の激しい仮想通貨市場では、トータルで負けているにもかかわらず、利益が出た年だけ多額の税金を支払わなければならない、という不公平な状況が生まれやすくなっています。
■ 世界と比べて日本の仮想通貨税金は高すぎ?主要国との税制比較
では、海外の税制はどうなっているのでしょうか。主要な国々と比較すると、日本の税負担の重さがより鮮明になります。
| 国・地域 | 課税方式の概要 | 最大税率(目安) |
|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 総合課税(給与などと合算) | 約55% |
| 🇺🇸 アメリカ | 分離課税(1年以上の長期保有で優遇) | 約20% (長期保有) |
| 🇬🇧 イギリス | 分離課税(キャピタルゲイン税) | 約20% |
| 🇩🇪 ドイツ | 1年以上の長期保有で非課税 | 0% (長期保有) |
| 🇸🇬 シンガポール | 個人による長期投資目的の売買は原則非課税 | 0% |
このように、多くの国では仮想通貨の利益を他の所得と切り離して課税する「申告分離課税」を採用したり、長期保有を優遇したりする制度を導入しています。これにより、Web3.0時代の新しい資産クラスを育成し、投資を促進する狙いがあります。結果として、優秀なエンジニアや起業家が、より税制の有利な国へ移住してしまう「Web3.0鎖国」や「仮想通貨難民」といった問題も指摘されています。
■ 「税金高すぎ」問題は解決する?仮想通貨の税制改正、今後の見通し【2025年最新】
こうした厳しい状況に対し、日本国内でも変化を求める声が年々高まっています。実際に、少しずつですが前進も見られます。
- 【実現済】法人税制の見直し
2024年度の税制改正で、法人が自社で発行して継続保有する仮想通貨について、期末の時価評価課税の対象外となりました。これにより、スタートアップがトークンを発行しやすくなるなど、ビジネス環境の改善が期待されます。 - 【議論中】個人の課税見直し
個人投資家の課税については、依然として大きな課題です。しかし、業界団体や一部の政治家からは、以下のような改正を求める声が強く上がっています。- 申告分離課税(税率20%程度)への変更
- 損失の繰越控除(3年間)の導入
- 仮想通貨同士の交換時における課税の繰り延べ
政府・与党内でも議論は続いており、Web3.0を国家戦略と位置づける流れの中で、2026年度以降の税制改正に向けた議論が本格化することが期待されています。
参考: 一般社団法人日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)「2024年度税制改正に関する要望書」■ 仮想通貨の税金が高すぎる今、私たちができる3つの対策
税制改正には時間がかかります。それまでの間、私たち投資家は現行のルールの中で賢く立ち回り、将来に備える必要があります。
- 1. 全ての取引履歴を記録・保管する
いつ、いくらで、どの仮想通貨を購入・売却したか、取引手数料はいくらかかったかなど、全ての取引履歴を正確に記録しておくことが確定申告の基本です。取引所の取引履歴ダウンロード機能などを活用しましょう。 - 2. 損益計算ツールを活用する
DeFiやNFT、複数の取引所を利用していると、手動での損益計算は非常に複雑で困難です。専用の損益計算ツールを使えば、取引履歴をアップロードするだけで自動的に計算してくれるため、申告作業が大幅に楽になり、計算ミスも防げます。

AIでかんたん確定申告
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する仮想通貨のAI損益計算サービスです。安心・かんたん・使いやすいサービスで、毎年の申告をスムーズに。
公式サイトで詳しく見る- 3. 早めに専門家(税理士)に相談する
利益が大きくなった場合や、取引が複雑な場合は、仮想通貨に詳しい税理士に相談することをお勧めします。節税に関するアドバイスを受けられたり、申告漏れによる追徴課税のリスクを回避したりできます。
■ 仮想通貨の「高すぎる税金」に関するQ&A
日本の仮想通貨税制は「高すぎる」と言われる厳しい状況ですが、変化の波は確実に訪れようとしています。重要なのは、以下の3点を押さえておくことです。
- 現状の理解: 仮想通貨の利益は最大55%の総合課税。損益通算や繰越控除ができない点を認識する。
- 将来への期待: 申告分離課税への変更など、税制改正の議論が進んでいることを知り、最新情報にアンテナを張る。
- 今すぐできる準備: 議論の行方を見守りつつ、正確な取引履歴の記録と損益計算ツールの活用で、来る確定申告に万全に備える。

この記事の監修者
村上 裕一(公認会計士・税理士)
公認会計士試験合格後、大手監査法人、メーカー経理財務、会計事務所を経て独立開業。仮想通貨・NFT・ブロックチェーンゲームを専門とする税理士として活躍。自らもSTEPNなどのブロックチェーンゲームなどをプレイし、多くの投資家の税務を支援している。
>> ホームページはこちら
💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
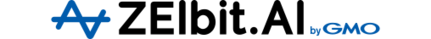
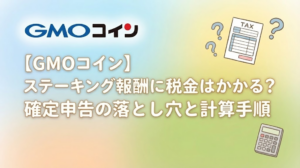


コメント 0件