【2025年最新】法人の暗号資産の税金を徹底解説!期末時価評価と税制改正のポイント
※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
この記事のポイント
■ 法人と個人の暗号資産税金、根本的な違いとは?
法人が暗号資産を扱う際の税務は、個人が直面するものとは構造的に大きく異なります。この違いを理解することは、税務戦略を立てる上での第一歩となります。主に「税率」「損益の扱い」「評価方法」の3つの点で決定的な差があります。
個人の場合、暗号資産の利益は原則「雑所得」として扱われ、給与など他の所得と合算して計算されます。所得が上がるほど税率も上がる「累進課税」が適用され、住民税と合わせると最大で約55%もの税率になります。
一方、法人の利益は暗号資産取引も含め全て合算され、法人税が課されます。実効税率は約30%〜35%程度で、個人の最高税率より低く抑えられるのが特徴です。 さらに、損失が出た場合の取り扱いも法人に大きなメリットがあります。
- 損益通算: 法人では、暗号資産取引の損失を本業の利益など、他の事業の利益と相殺できます。これにより法人全体の課税所得を圧縮可能です。
- 繰越控除: 事業年度全体で赤字(欠損金)が出た場合、その損失を最長10年間繰り越し、将来の利益と相殺できます。 個人ではこれらの扱いは認められていません。
- 期末時価評価課税: これが最も重要な違いです。法人は、期末に保有する暗号資産の「含み益」に対しても課税されます。つまり、売却していなくても、価格が上がっただけで税金を支払う必要があるのです。 個人は売却して利益が確定するまで課税されません。
| 特徴 | 個人 (Individual) | 法人 (Corporation) |
|---|---|---|
| 所得区分 | 雑所得(原則) | 法人所得(全事業合算) |
| 適用税率 | 総合課税・累進税率(最大約55%) | 法人税率(実効税率約30-35%) |
| 損益通算 | 不可 | 可(全事業の損益と通算) |
| 損失の繰越控除 | 不可 | 可(欠損金を最長10年) |
| 期末の含み益 | 課税対象外 | 課税対象(原則、期末時価評価) |
■ 法人での利益計算方法と課税されるタイミング
法人税を正しく計算するには、「いつ利益が認識されるか(課税タイミング)」と「どうやって利益を計算するか(所得計算方法)」を理解する必要があります。
課税タイミングは主に以下の4つです。
- 売却時: 暗号資産を日本円などに換金した時。
- 決済利用時: 暗号資産で商品やサービスを購入した時。
- 他の暗号資産との交換時: ビットコインをイーサリアムに交換するなど、異なる暗号資産を交換した時。
- マイニング・ステーキング等での取得時: 報酬として暗号資産を受け取った時。
利益を計算する上で核となるのが「取得価額」です。法人は、暗号資産の種類ごとに「移動平均法」か「総平均法」のどちらかを選択して計算します。
- 移動平均法: 暗号資産を購入するたびに、平均取得単価を計算し直す方法です。届出をしない場合は原則この方法が適用されます。 取引ごとの損益を正確に把握できるメリットがあります。
- 総平均法: 事業年度内の購入総額を、購入総数量で割って一度に平均単価を出す方法です。計算は簡単ですが、期末まで損益が確定しないデメリットがあります。
■ 最大の課題「法人 暗号資産 税金」の核心、期末時価評価課税と最新の税制改正
法人の暗号資産税務で最も大きな課題が「期末時価評価課税」です。これは、事業年度の終わりに保有している暗号資産をその時点の時価で評価し、帳簿価額との差額(含み益・含み損)をその期の利益または損失として計上する制度です。
最大の問題は、まだ売却していない未実現の利益(含み益)に課税される点です。 これにより、納税資金を確保するために、長期保有目的の暗号資産を売却せざるを得ないケースがあり、Web3事業者の成長を妨げる要因と指摘されてきました。
この問題に対応するため、近年、段階的な税制改正が行われています。
- 令和5年度(2023年)改正: 自社で発行し、譲渡制限などの要件を満たす暗号資産(特定自己発行暗号資産)は、期末時価評価の対象外となりました。これにより、Web3プロジェクトの発行体自身の税負担が軽減されました。
- 令和6年度(2024年)改正: さらに緩和が進み、第三者が保有する暗号資産であっても、一定の譲渡制限が付されているもの(特定譲渡制限付暗号資産)については、「時価評価」か「原価評価(時価評価しない)」かを選択できるようになりました。 これにより、ベンチャーキャピタルなども含み益への課税を回避しつつ、プロジェクトを長期的に支援しやすくなったのです。
| 適用時期 | 時価評価の対象となる暗号資産 | 時価評価の対象外となる暗号資産 |
|---|---|---|
| 改正前 | 活発な市場が存在する全ての暗号資産 | なし |
| 令和5年度改正後 | 上記から特定自己発行暗号資産を除く | ・特定自己発行暗号資産 |
| 令和6年度改正後 | 上記から特定譲渡制限付暗号資産(原価法選択時)を除く | ・特定自己発行暗号資産 ・特定譲渡制限付暗号資産(原価法を選択した場合) |
■ 実践的な会計処理と税務申告の「ズレ」を調整する方法
法人は、会計上のルール(企業会計基準)と税法上のルールの両方に従う必要があります。この2つのルールは必ずしも一致せず、特に前述の税制改正によってその「ズレ」が大きくなりました。 このズレを調整する手続きが「申告調整」です。
例えば、法人が「特定譲渡制限付暗号資産」を保有しているケースを考えてみましょう。
- 会計上: 「活発な市場がある」と判断し、期末に時価評価を行い、1,000万円の評価益を計上。
- 税務上: 税制改正の特例を使い「原価法」を選択。この場合、1,000万円の評価益は課税対象になりません。
この場合、会計上の利益には1,000万円の評価益が含まれていますが、税務上の課税所得には含まれません。そのため、法人税の申告書(別表四)で、会計上の利益からこの1,000万円を差し引く(減算する)調整が必要になります。これを「益金不算入」と呼びます。 このように、会計と税務の違いを正しく理解し、申告調整を行うことが極めて重要です。

AIでかんたん確定申告
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する暗号資産のAI損益計算サービスです。安心・かんたん・使いやすいサービスで、毎年の申告をスムーズに。
公式サイトで詳しく見る■ DeFi・NFTなど高度な取引の法人税金はどうなる?
暗号資産の取引は単純な売買だけではありません。マイニングやNFT、DeFiといった高度な取引には、それぞれ特有の税務上の論点があります。
- マイニング・ステーキング: 報酬として暗号資産を受け取った時点で、その時の時価が収益として認識されます。 マイニングマシンなどの関連費用は経費として計上できます。
- NFT(非代替性トークン): NFTを制作して販売した場合や、購入したNFTを転売して得た利益は法人所得となります。 注意点として、NFTを暗号資産(例: ETH)で購入した場合、そのETHを支払った時点で譲渡損益が発生し、課税対象となります。 また、NFTの売買は消費税の課税対象となる点も暗号資産と異なります。
- DeFi(分散型金融): 法人税務において最も解釈が定まっていないグレーゾーンです。 特に、流動性プールに暗号資産を預け入れ「LPトークン」を受け取る取引が、課税対象となる「譲渡」にあたるかについては専門家の間でも見解が分かれています。 この不確実性は企業にとって大きなリスクとなるため、専門家と協議の上で方針を決定し、その根拠を記録しておくことが重要です。
■ 暗号資産取引の法人化、メリット・デメリットと判断基準
暗号資産で大きな利益を得た個人投資家にとって「法人化」は重要な選択肢です。しかし、メリットとデメリットを総合的に判断する必要があります。
法人化を検討する一つの目安は、年間の利益が800万円〜900万円を超えるあたりです。 この水準を超えると、個人の所得税・住民税を合わせた税率が、法人税の実効税率を上回る可能性が高くなります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ✅ 税率の上限が低い(約30-35%) | ❌ 期末時価評価課税のリスクがある |
| ✅ 損益通算ができる | ❌ 設立・維持コストがかかる(登記費用、税理士報酬など) |
| ✅ 損失を10年間繰り越せる | ❌ 事務負担が増大する(複雑な会計・申告) |
| ✅ 経費にできる範囲が広がる(役員報酬など) | ❌ 赤字でも法人住民税(均等割)が発生する |
法人化は単に税率だけで判断するのではなく、これらの要素を総合的に勘案し、長期的な事業計画に基づいて決定すべき重要な経営判断です。
■ 今後の税制改正の展望と世界の動向
日本の暗号資産税制は、グローバルな競争の中で変化し続けています。業界団体からは、個人の税制を株式などと同じ「申告分離課税(税率約20%)」にすることや、暗号資産同士の交換時には課税しないことなどを求める要望が毎年提出されています。
世界の法人税制と比較すると、日本の「期末時価評価課税」はグローバルスタンダードから見れば厳しいルールでした。 シンガポールやスイス、ドバイなどは、より有利な税制を整備し、多くのWeb3企業を惹きつけています。
近年の期末時価評価課税の緩和は、こうした海外への企業・人材流出を防ぎ、国際競争力を維持するための重要な一歩と言えます。 今後も、国内のWeb3産業を育成するため、さらなる税制改正が進むことが期待されます。
■ よくある質問(Q&A)
法人における暗号資産の税務は、個人と比べて低い税率や損益通算・繰越控除といった強力なメリットがあります。一方で、最大のハードルである「期末時価評価課税」の存在を忘れてはいけません。近年の税制改正でこのルールは緩和されましたが、その適用要件は複雑です。法人化を検討する際は、目先の税率だけでなく、設立・維持コストや事務負担、そして納税資金の確保といったデメリットも総合的に考慮することが成功の鍵です。暗号資産を事業に組み込む際は、必ず税理士などの専門家と相談しましょう。
💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
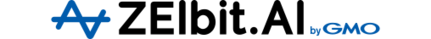
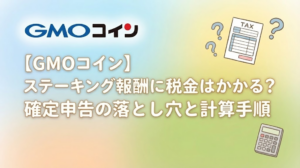


コメント 0件