税金に関するお役立ち情報
【2025年最新版】仮想通貨の税金で知っておきたいこと|確定申告・所得計算・必要経費まで徹底解説
最近、仮想通貨(暗号資産)を始めたんだけど、利益が出たら税金がかかるって本当?何だかルールが複雑そうで、何をどうすればいいのか全然分からないんだ…。🤔
仮想通貨と税金、最初は戸惑いますよね。でも大丈夫です!基本的なルールさえ押さえておけば、決して難しいものではありません。今日は「仮想通貨の税金 完全ガイド」として、ゼロから分かりやすく解説していきますので、一緒に学んでいきましょう!
■ まずはココから!利益(所得)が生まれる4つのタイミング
「仮想通貨を持っているだけ」では税金はかかりません。税金が発生するのは、取引によって利益が確定したタイミングです。具体的には、主に以下の4つのケースで利益(所得)が認識されます。
- 1. 売却:仮想通貨を日本円や米ドルなどの法定通貨に換金して利益が出た場合。
- 2. 決済:仮想通貨を使って商品やサービスを購入した場合。その時点の時価で売却したとみなされます。
- 3. 交換:ビットコイン(BTC)でイーサリアム(ETH)を購入するなど、ある仮想通貨を別の仮想通貨に交換した場合。
- 4. 取得(マイニング等):マイニング、ステーキング、エアドロップなどで新たに仮想通貨を取得した場合。取得時点の時価が所得となります。
■ どうやって計算する?所得計算の基本と2つの評価方法
仮想通貨の所得は、シンプルな計算式「売却価格 − 必要経費(取得価額など)」で求められます。この「取得価額」をどう計算するかについて、国税庁は2つの方法を認めています。
「移動平均法」と「総平均法」…なんだか難しそう。どっちを選べばいいんだろう?
良い質問ですね。これは非常に重要な選択で、一度選ぶと原則として3年間は変更できません。それぞれの特徴を理解して、ご自身の投資スタイルに合った方を選びましょう。
| 評価方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 移動平均法 | 仮想通貨を購入する都度、取得価額を更新していく方法。 | 期中でも損益を把握しやすい。 | 計算が非常に複雑になる。 |
| 総平均法 | 1年間の総購入金額を総購入数量で割り、平均単価を算出する方法。 | 年1回の計算で済むため、比較的シンプル。 | 年末まで損益が確定しない。 |
取引回数が多い方は計算がシンプルな総平均法、こまめに損益を管理したい方は移動平均法が向いていると言えますが、手計算は困難なため、どちらを選ぶにせよ損益計算ツールの利用が推奨されます。
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する暗号資産のAI損益計算サービスです。「移動平均法」「総平均法」の両方に対応。取引所のデータをアップロードするだけで、複雑な計算を自動で行い、確定申告を強力にサポートします。 

■ 確定申告が必要になるのはどんな人?
仮想通貨の利益は、原則として「雑所得」に分類されます。会社員(給与所得者)の方の場合、給与以外の所得、つまり仮想通貨を含む雑所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
また、専業主婦(主夫)や学生の方など、扶養に入っている場合は、合計所得金額が48万円(基礎控除額)を超えると申告が必要になるケースが多いので注意が必要です。
■ 申告で失敗しないための3つの鉄則
最後に、申告時に慌てないために、日頃から心がけておきたい3つのポイントをご紹介します。
-
1. 全ての取引履歴を保管する
どの取引所で、いつ、何を、いくらで売買したか、全ての記録が必要です。取引所が提供する年間取引報告書だけでなく、CSV形式の取引履歴も必ずダウンロードして保管しましょう。 -
2. 必要経費の領収書を保管する
売買手数料はもちろん、情報収集のための書籍代やセミナー参加費、税金計算ツールの利用料なども経費にできる場合があります。日付、金額、内容がわかる領収書やレシートを整理しておきましょう。 -
3. 迷ったら専門家を頼る
取引が複雑な場合や、事業として取引を行っている場合など、判断に迷うことがあれば、税務署や税理士などの専門家に相談することが最も確実な方法です。
💡 今日のまとめ:仮想通貨の税金、これだけは押さえよう!
- 仮想通貨は、売却・決済・交換・取得(マイニング等)のタイミングで利益が確定し、課税対象となります。
- 所得の計算方法には「移動平均法」と「総平均法」があり、自分の投資スタイルに合った方を選びます。
- 会社員の場合、仮想通貨などの利益が年間20万円を超えたら、翌年に確定申告が必要です。
- 日頃から全ての取引履歴と経費の領収書を整理・保管しておくことが、正しい申告への一番の近道です。
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
免責事項
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
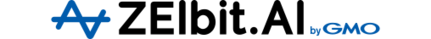
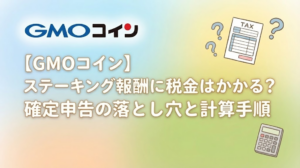


コメント 0件