„ÄźŚąĚŚŅÉŤÄÖ„āāŚģČŚŅÉ„ÄĎśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎŚÖ•ťĖÄÔĹúŤ®ąÁģóśĖĻś≥ē„Ā®ÁĘļŚģöÁĒ≥ŚĎä„ĀģŚüļśú¨
śúÄŤŅĎ„ÄĀ„ÄĆ„É™„ā≠„ÉÉ„ÉČ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Äć„Ā™„āď„Ā¶Ť®ÄŤĎČ„āāŤĀě„ĀŹ„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„ÄāśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£„āíśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā†„ĀĎ„Āߌ†ĪťÖ¨„ĀĆ„āā„āČ„Āą„āč„Āģ„ĀĮť≠ÖŚäõÁöĄ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀšĽēÁĶĄ„ĀŅ„ĀĆŤ§áťõĎ„Āę„Ā™„āč„ĀĽ„Ā©Á®éťáĎ„Āģ„Āď„Ā®„ĀĆŚŅÉťÖć„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô‚Ķ
Áī†śôī„āČ„Āó„ĀĄŤ¶ĖÁāĻ„Āß„Āô„Ā≠ÔľĀ„Āä„Ā£„Āó„āÉ„āčťÄö„āä„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„āĄ„É™„ā≠„ÉÉ„ÉČ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Āߌĺó„ĀüŚ†ĪťÖ¨„Āę„ĀĮÁ®éťáĎ„ĀĆ„Āč„Āč„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁü•„āČ„Ā™„ĀĄ„Āĺ„Āĺ„Ā†„Ā®„ÄĀŚĺĆ„ĀßśÄĚ„āŹ„Ā¨ŤŅĹŚĺīŤ™≤Á®é„ĀęÁĻč„ĀĆ„āč„Āď„Ā®„āā„ÄāšĽäŚõě„ĀĮ„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āįŚ†ĪťÖ¨„ĀģÁ®éťáĎ„ĀģŚüļśú¨„Āč„āČ„ÄĀŤ§áťõĎ„Ā™DeFiŚŹĖŚľē„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ÁĒ≥ŚĎäśľŹ„āĆ„Āģ„É™„āĻ„āĮ„Āĺ„Āß„ÄĀŚÖ®šĹďŚÉŹ„ā팹܄Āč„āä„āĄ„Āô„ĀŹŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„ĀôÔľĀ
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
- „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āįŚ†ĪťÖ¨„Āę„Āč„Āč„āčÁ®éťáĎ„ĀģŚüļśú¨Ôľö„ĀĄ„Ā§„ÄĀ„ĀĄ„ĀŹ„āČŤ™≤Á®é„Āē„āĆ„āčÔľü
- „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎŤ®ąÁģóÔľöŚÖ∑šĹďšĺč„Āߍ¶č„āčśČÄŚĺó„ĀģŤ®ąÁģóśĖĻś≥ē
- „ÄźŚŅúÁĒ®Á∑®„ÄĎ„É™„ā≠„ÉÉ„ÉČ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎ„ĀĮÔľüDeFi„ĀģŤ§áťõĎ„Ā™Á®éŚčôŚá¶ÁźÜ
- „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Ā®Á®éťáĎÔľöÁĘļŚģöÁĒ≥ŚĎä„Āßśäľ„Āē„Āą„āč„ĀĻ„Āć3„Ā§„Āģťá捶Ā„ÉĚ„ā§„É≥„Éą
- „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎÁĒ≥ŚĎäśľŹ„āĆ„ĀĮŚćĪťôļÔľĀÁ®éŚčôŤ™ŅśüĽ„Ā®„Éö„Éä„Éę„ÉÜ„ā£„Āģ„É™„āĻ„āĮ
- „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎ„ĀęťĖĘ„Āô„āčQ&A
‚Ė† „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āįŚ†ĪťÖ¨„Āę„Āč„Āč„āčÁ®éťáĎ„ĀģŚüļśú¨Ôľö„ĀĄ„Ā§„ÄĀ„ĀĄ„ĀŹ„āČŤ™≤Á®é„Āē„āĆ„āčÔľü
ÁĶźŤęĖ„Āč„āČŤ®Ä„ĀÜ„Ā®„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Āߌĺó„ĀüŚ†ĪťÖ¨„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀģÁ®éś≥ēšłä„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĆťõĎśČÄŚĺó„Äć„Āꌹܝ°ě„Āē„āĆ„ÄĀŤ™≤Á®éŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāśúÄ„āāťá捶Ā„Ā™„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚ†ĪťÖ¨„ā팏ó„ĀĎŚŹĖ„Ā£„ĀüśôāÁāĻ„Äć„ĀßśČÄŚĺó„ĀĆŤ™ćŤ≠ė„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā
„Āď„āĆ„ĀĮ„Ā§„Āĺ„āä„ÄĀŚ†ĪťÖ¨„āíśó•śú¨ŚÜÜ„Āęšļ§śŹõ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀŹ„Ā¶„āā„ÄĀ„ā¶„ā©„ɨ„ÉÉ„Éą„ĀęśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£„ĀĆšĽėšłé„Āē„āĆ„ĀüÁ쨝Ėď„Āę„ÄĀ„ĀĚ„Āģśôā„Āģšĺ°ś†ľÔľąśôāšĺ°ÔľČ„ĀßśČÄŚĺó„ā퍮ąÁģó„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģ„ÄĆśôāšĺ°Ť©ēšĺ°„Äć„ĀĆ„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎŤ®ąÁģó„ā퍧áťõĎ„Āę„Āô„āčśúÄŚ§ß„ĀģŤ¶ĀŚõ†„Ā®Ť®Ä„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
‚Ė† „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎŤ®ąÁģóÔľöŚÖ∑šĹďšĺč„Āߍ¶č„āčśČÄŚĺó„ĀģŤ®ąÁģóśĖĻś≥ē
Ť®ÄŤĎČ„Ā†„ĀĎ„Āß„ĀĮŚąÜ„Āč„āä„Āę„ĀŹ„ĀĄ„Āģ„Āß„ÄĀÁį°Śćė„Ā™šĺč„Āߍ¶č„Ā¶„ĀŅ„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„ÄāšĽģ„Āę„Āā„Ā™„Āü„ĀĆA„ā≥„ā§„É≥„āí„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Āó„Ā¶„ÄĀśĮéśúąŚ†ĪťÖ¨„āíŚĺó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®„Āó„Āĺ„Āô„Äā
| Ś†ĪťÖ¨ŚŹóŚŹĖśó• | Ś†ĪťÖ¨śēįťáŹ (A„ā≥„ā§„É≥) | ŚŹóŚŹĖśôā„Āģśôāšĺ° (1A„ā≥„ā§„É≥„Āā„Āü„āä) | śČÄŚĺóťáĎť°ć (ŚÜÜ) |
|---|---|---|---|
| 2025ŚĻī4śúą15śó• | 10 A | 500ŚÜÜ | 5,000ŚÜÜ |
| 2025ŚĻī5śúą15śó• | 10 A | 550ŚÜÜ | 5,500ŚÜÜ |
| 2025ŚĻī6śúą15śó• | 10 A | 480ŚÜÜ | 4,800ŚÜÜ |
| „Āď„ĀģśúüťĖď„ĀģŚźąŤ®ąśČÄŚĺó | 15,300ŚÜÜ | ||
„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀŚ†ĪťÖ¨„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„āč„Āü„Ā≥„Āę„ÄĀ„ĀĚ„Āģśó•„Āģ„ɨ„Éľ„Éą„Āßśó•śú¨ŚÜÜ„Ā꜏õÁģó„Āó„ÄĀŤ®ėťĆ≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāśĮéśó•„āĄśĮéťÄĪ„Āģ„āą„ĀÜ„ĀꌆĪťÖ¨„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„ā茆īŚźą„ÄĀ„Āď„ĀģśČčšĹúś•≠„ĀĮťĚ쌳ł„ĀęÁÖ©ťõĎ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
‚Ė† „ÄźŚŅúÁĒ®Á∑®„ÄĎ„É™„ā≠„ÉÉ„ÉČ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎ„ĀĮÔľüDeFi„ĀģŤ§áťõĎ„Ā™Á®éŚčôŚá¶ÁźÜ
ŤŅĎŚĻī„Āß„ĀĮ„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Āó„ĀüŤ≥áÁĒ£„āí„Āē„āČ„Āꌹ•„Āģ„Éó„É≠„Éą„ā≥„Éę„Āߌą©ÁĒ®„Āô„āč„ÄĆ„É™„ā≠„ÉÉ„ÉČ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Äć„āĄ„ÄĆ„É™„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Äć„ĀĆšłĽśĶĀ„Āę„Ā™„āä„Ā§„Ā§„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀ„ā§„Éľ„āĶ„É™„āʄɆ„āí„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Āó„Ā¶stETH„ā팏ó„ĀĎŚŹĖ„āä„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āí„Āē„āČ„ĀęDeFi„Éó„É≠„Éą„ā≥„Éę„ĀßťĀčÁĒ®„Āô„āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„āĪ„Éľ„āĻ„Āß„Āô„Äā
„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ť§áťõĎ„Ā™ŚŹĖŚľē„Āß„āā„ÄĀŤ™≤Á®é„ĀģŚéüŚČá„ĀĮŚźĆ„Āė„Āß„Āô„ÄāLRTÔľą„É™„ā≠„ÉÉ„ÉČ„ÉĽ„É™„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ÉĽ„Éą„Éľ„āĮ„É≥ԾȄĀģ„āą„ĀÜ„Ā™Ś†ĪťÖ¨„Éą„Éľ„āĮ„É≥„ā팏ó„ĀĎŚŹĖ„Ā£„ĀüÔľąŤęčśĪāś®©„ĀĆÁĘļŚģö„Āó„ĀüԾȜôāÁāĻ„Āß„ÄĀ„ĀĚ„Āģśôā„Āģśôāšĺ°„ĀęŚüļ„Ā•„ĀĄ„Ā¶śČÄŚĺó„ā퍙ćŤ≠ė„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ĀĄ„Ā§„āí„ÄĆÁĘļŚģö„Āó„ĀüśôāÁāĻ„Äć„Ā®śćČ„Āą„āč„Āč„ÄĀ„Ā©„Āģšĺ°ś†ľ„āí„ÄĆśôāšĺ°„Äć„Ā®„Āô„āč„Āč„ĀĮ„ÄĀ„Éó„É≠„Éą„ā≥„Éę„Āę„āą„Ā£„Ā¶Áēį„Ā™„āä„ÄĀťĚ쌳ł„Āꌹ§śĖ≠„ĀĆťõ£„Āó„ĀĄ„Āģ„ĀĆŚģüśÉÖ„Āß„Āô„Äā
- ś®©Śą©ÁĘļŚģö„Āģ„āŅ„ā§„Éü„É≥„āį: Ś†ĪťÖ¨„ĀĆ„ĀĄ„Ā§„Āß„āāŚľē„ĀćŚáļ„Āõ„āčÁä∂śÖč„Āę„Ā™„Ā£„ĀüśôāÁāĻ„Ā™„Āģ„Āč„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„Ā®„āāÁČĻŚģö„ĀģśďćšĹú„āí„Āó„ĀüśôāÁāĻ„Ā™„Āģ„Āč„Äā
- śôāšĺ°„ĀģŚŹĖŚĺó: ŚąÜśē£Śě茏ĖŚľēśČÄÔľąDEXԾȄĀß„ĀģśĶĀŚčēśÄß„ĀĆšĹé„ĀĄ„Éą„Éľ„āĮ„É≥„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀś≠£ÁĘļ„Ā™śôāšĺ°„āíśä䜏°„Āô„āč„Āď„Ā®Ťá™šĹď„ĀĆŚõįťõ£„Äā
- ŚŹĖŚľēŚĪ•ś≠ī„ĀģŤŅĹŤ∑°: Ť§áśēį„Āģ„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇ„āí„Āĺ„Āü„ĀĄ„Ā†ŚŹĖŚľēŚĪ•ś≠ī„āí„Āô„ĀĻ„Ā¶śČčŚčē„ĀߌŹéťõÜ„ÉĽśēīÁźÜ„Āô„āč„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„ĀĽ„ĀľšłćŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„Äā
„Āď„āĆ„āČ„ĀģŚŹĖŚľē„āíśČ荮ąÁģó„Āßś≠£ÁĘļ„ĀęŤŅĹŤ∑°„ÉĽŤ®ąÁģó„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮÁŹĺŚģüÁöĄ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀŚįāťĖÄÁöĄ„Ā™Áü•Ť≠ė„Ā®„ÉĄ„Éľ„Éę„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā

AI„Āß„Āč„āď„Āü„āďÁĘļŚģöÁĒ≥ŚĎä
ZEIbit.AI„ĀĮGMO„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éą„āį„Éę„Éľ„Éó„ĀĆśŹźšĺõ„Āô„āčśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£„ĀģAIśźćÁõ䍮ąÁģó„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„Āß„Āô„ÄāŚģČŚŅÉ„ÉĽ„Āč„āď„Āü„āď„ÉĽšĹŅ„ĀĄ„āĄ„Āô„ĀĄ„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„Āß„ÄĀŤ§áťõĎ„Ā™„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„āĄDeFi„ĀģŚŹĖŚľē„āāŤá™ŚčēŤ®ąÁģó„ÄāśĮéŚĻī„ĀģÁĒ≥ŚĎä„āí„āĻ„Ɇ„Éľ„āļ„Āę„Äā
ŚÖ¨ŚľŹ„āĶ„ā§„Éą„Āߍ©≥„Āó„ĀŹŤ¶č„āč‚Ė† „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„Ā®Á®éťáĎÔľöÁĘļŚģöÁĒ≥ŚĎä„Āßśäľ„Āē„Āą„āč„ĀĻ„Āć3„Ā§„Āģťá捶Ā„ÉĚ„ā§„É≥„Éą
- ÁĒ≥ŚĎä„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā™„Āģ„ĀĮ„ĀĄ„Ā§Ôľü: šľöÁ§ĺŚď°„Ā™„Ā©„ĀģÁĶ¶šłéśČÄŚĺóŤÄÖ„ĀģśĖĻ„Āß„āā„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āįŚ†ĪťÖ¨„ā팟ę„āÄśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£„ĀģśČÄŚĺóÔľąťõĎśČÄŚĺóԾȄĀĆŚĻīťĖď20šłáŚÜÜ„āíŤ∂Ö„Āą„ĀüŚ†īŚźą„ĀĮ„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶ÁĘļŚģöÁĒ≥ŚĎä„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā
- śĶ∑Ś§ĖŚŹĖŚľēśČÄ„ĀģŚ†ĪťÖ¨„āāŚĮĺŤĪ°: śó•śú¨„ĀęšĹŹ„āď„Āß„ĀĄ„ā茆īŚźą„ÄĀ„Ā©„ĀģŚõĹ„ĀģŚŹĖŚľēśČÄ„āĄDeFi„Éó„É≠„Éą„ā≥„Éę„ā팹©ÁĒ®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā¶„āā„ÄĀŚĺó„āČ„āĆ„ĀüśČÄŚĺó„ĀĮŚÖ®„Ā¶śó•śú¨„ĀģÁ®éťáĎ„ĀģŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„ĀôÔľąŚÖ®šłĖÁēĆśČÄŚĺóŤ™≤Á®éԾȄÄā
- Ťá™ŚčēŚÜć„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„āāŤ™≤Á®éŚĮĺŤĪ°: Ś†ĪťÖ¨„ĀĆÁõīśé•„ā¶„ā©„ɨ„ÉÉ„Éą„ĀęťÄĀ„āČ„āĆ„Āö„ÄĀŤá™ŚčēÁöĄ„ĀęŚÜćŚļ¶„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀęŚõě„Āē„āĆ„āčÔľąŤ§áŚą©ťĀčÁĒ®„Āē„āĆ„āčԾȌ†īŚźą„Āß„āā„ÄĀŚ†ĪťÖ¨„ĀĆś®©Śą©„Ā®„Āó„Ā¶ÁĘļŚģö„Āó„ĀüśôāÁāĻ„ĀßśČÄŚĺó„Ā®„Āó„Ā¶Ť™ćŤ≠ė„Āē„āĆ„ÄĀŤ™≤Á®éŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āčÁāĻ„Āęś≥®śĄŹ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā
‚Ė† „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎÁĒ≥ŚĎäśľŹ„āĆ„ĀĮŚćĪťôļÔľĀÁ®éŚčôŤ™ŅśüĽ„Ā®„Éö„Éä„Éę„ÉÜ„ā£„Āģ„É™„āĻ„āĮ
„ÄĆŚįĎť°ć„Ā†„Āč„āČ„Äć„ÄĆśĶ∑Ś§Ė„ĀģŚŹĖŚľē„Ā†„Āč„āČ„Éź„ɨ„Ā™„ĀĄ„Ā†„āć„ĀÜ„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤÄÉ„Āą„ĀĮťĚ쌳ł„ĀęŚćĪťôļ„Āß„Āô„ÄāŚõĹÁ®éŚļĀ„ĀĮŤŅĎŚĻī„ÄĀśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£ŚŹĖŚľē„ĀęŚĮĺ„Āô„āčÁõ£Ť¶Ė„ā팾∑ŚĆĖ„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀCRSÔľąŚÖĪťÄöŚ†ĪŚĎäŚüļśļĖԾȄĀ™„Ā©„ĀģŚõĹťöõÁöĄ„Ā™śÉÖŚ†Īšļ§śŹõÁ∂≤„āíťÄö„Āė„Ā¶„ÄĀśĶ∑Ś§ĖŚŹĖŚľēśČÄ„ĀģśÉÖŚ†Ī„āāśä䜏°„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ÁĒ≥ŚĎäśľŹ„āĆ„ĀĆÁôļŤ¶ö„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀśú¨śĚ•Áīć„āĀ„āč„ĀĻ„ĀćÁ®éťáĎ„ĀęŚä†„Āą„Ā¶„ÄĀ„Éö„Éä„Éę„ÉÜ„ā£„Ā®„Āó„Ā¶šĽ•šłč„ĀģŤŅĹŚĺīŤ™≤Á®é„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
- ÁĄ°ÁĒ≥ŚĎäŚä†ÁģóÁ®é: śúüťôźŚÜÖ„ĀęÁĒ≥ŚĎä„Āó„Ā™„Āč„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„Āꍙ≤„Āē„āĆ„ÄĀÁ®éť°ć„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶śúÄŚ§ß20%„ĀĆŚä†Áģó„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
- ťĀéŚįĎÁĒ≥ŚĎäŚä†ÁģóÁ®é: ÁĒ≥ŚĎä„Āó„ĀüÁ®éť°ć„ĀĆŚįĎ„Ā™„Āč„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„Āꍙ≤„Āē„āĆ„ÄĀŤŅĹŚä†ÁīćÁ®éť°ć„Āģ10%„Äú15%„ĀĆŚä†Áģó„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
- ťáćŚä†ÁģóÁ®é: śĄŹŚõ≥ÁöĄ„Ā™śČÄŚĺóťö†„Āó„Ā™„Ā©„ÄĀśā™Ť≥™„Ā®Śą§śĖ≠„Āē„āĆ„ĀüŚ†īŚźą„Āꍙ≤„Āē„āĆ„ÄĀśúÄŚ§ß40%„Ā®„ĀĄ„ĀÜťĚ쌳ł„Āęťáć„ĀĄ„Éö„Éä„Éę„ÉÜ„ā£„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
- ŚĽ∂śĽěÁ®é: Áī暼ėśúüťôź„ĀģÁŅĆśó•„Āč„āČÁī暼ė„Āô„āčśó•„Āĺ„Āß„Āģśó•śēį„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶Ť™≤„Āē„āĆ„ā茹©śĀĮÁöĄ„Ā™Á®éťáĎ„Āß„Āô„Äā
‚Ė† „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀģÁ®éťáĎ„ĀęťĖĘ„Āô„āčQ&A
„Ā™„āč„ĀĽ„Ā©‚Ķ„Äā„Āß„ĀĮ„ÄĀŚ†ĪťÖ¨„Āß„āā„āČ„Ā£„ĀüA„ā≥„ā§„É≥„āí„ÄĀŚĺĆ„Āߌħšłä„ĀĆ„āä„Āó„Āüśôā„ĀęŚ£≤„Ā£„Āü„āČ„ÄĀ„ĀĚ„Āģśôā„āā„Āĺ„ĀüÁ®éťáĎ„ĀĆ„Āč„Āč„āč„āď„Āß„Āô„ĀčÔľüšļĆťá捙≤Á®é„ĀŅ„Āü„ĀĄ„Āßśźć„Āó„ĀüśįóŚąÜ„Āß„Āô„Äā
„ĀĚ„Āď„ĀĆťá捶Ā„Ā™„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„Āß„ĀôÔľĀÁĶźŤęĖ„Āč„āČŤ®Ä„ĀÜ„Ā®šļĆťá捙≤Á®é„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāŚ†ĪťÖ¨„Āß„āā„āČ„Ā£„ĀüśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£„āíŚ£≤Śćī„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀ„ÄĆŚ£≤Śćīśôā„Āģšĺ°ś†ľ„Äć„Ā®„ÄĆŚ†ĪťÖ¨„ā팏ó„ĀĎŚŹĖ„Ā£„Āüśôā„Āģšĺ°ś†ľÔľąÔľĚŚŹĖŚĺóšĺ°ť°ćԾȄÄć„Ā®„ĀģŚ∑ģť°ć„ĀĆ„ÄĀśĖį„Āü„ĀęśČÄŚĺóÔľą„Āĺ„Āü„ĀĮśźćŚ§ĪԾȄĀ®„Āó„Ā¶Ť®ąÁģó„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
šĺč„Āą„Āį„ÄĀŚÖą„Āģšĺč„Āßśôāšĺ°500ŚÜÜ„ĀߌŹó„ĀĎŚŹĖ„Ā£„Āü1A„ā≥„ā§„É≥„āí„ÄĀŚĺĆ„Āę800ŚÜÜ„Āߌ£≤Śćī„Āó„Āü„Ā®„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀŚ∑ģť°ć„Āģ300ŚÜÜÔľąŚ£≤Śćīšĺ°ś†ľ800ŚÜÜ – ŚŹĖŚĺóšĺ°ť°ć500ŚÜÜԾȄĀĆŚ£≤Śćī„Āę„āą„āčśČÄŚĺó„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚŹĖŚĺóšĺ°ť°ć„ĀĆ0ŚÜÜ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āü„āĀ„ÄĀś≠£„Āó„ĀŹŤ®ąÁģó„Āô„āĆ„ĀįšļĆťáć„Āꍙ≤Á®é„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āģ„Āß„Āô„Äā
„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„āí„Āô„āč„Āü„āĀ„Āģ„ÉĎ„āĹ„ā≥„É≥„ĀģťõĽśįóšĽ£„āĄ„ÄĀśÉÖŚ†ĪŚŹéťõÜ„Āģ„Āü„āĀ„ĀģťÄöšŅ°Ť≤Ľ„Ā™„Ā©„ĀĮÁĶĆŤ≤Ľ„Āę„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ĀčÔľü
„ĀĮ„ĀĄ„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āįŚ†ĪťÖ¨„āíŚĺó„āč„Āü„āĀ„ĀęÁõīśé•ŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„Ā£„ĀüŤ≤ĽÁĒ®„ĀĮ„ÄĀŚŅÖŤ¶ĀÁĶĆŤ≤Ľ„Ā®„Āó„Ā¶śČÄŚĺó„Āč„āČŚ∑ģ„ĀóŚľē„ĀĎ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀśźćÁõ䍮ąÁģó„ÉĄ„Éľ„Éę„ĀģŚą©ÁĒ®śĖô„āĄ„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āį„ĀęťĖĘ„Āô„āč„āĽ„Éü„Éä„ÉľŚŹāŚä†Ť≤Ľ„Ā™„Ā©„ĀĆŤ©≤ŚĹď„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀ„ÉĎ„āĹ„ā≥„É≥šĽ£„āĄťÄöšŅ°Ť≤Ľ„Āģ„āą„ĀÜ„ĀęÁßĀÁĒüśīĽ„Ā®ŚÖĪÁĒ®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„āā„Āģ„ĀĮ„ÄĀšĹŅÁĒ®śôāťĖď„Ā™„Ā©„ĀߌźąÁźÜÁöĄ„ĀęśĆČŚąÜÔľąŚģ∂šļčśĆČŚąÜԾȄĀó„Ā¶Ť®ąÁģó„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Ā©„Āď„Āĺ„Āß„ĀĆÁĶĆŤ≤Ľ„Ā®„Āó„Ā¶Ť™ć„āĀ„āČ„āĆ„āč„Āč„ÄĀśúÄÁĶāÁöĄ„Ā™Śą§śĖ≠„ĀĮÁ®éŚčôÁĹ≤„āĄÁ®éÁźÜŚ£ę„Āę„ĀĒÁõłŤęá„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā
śú¨Ť®ėšļč„ĀģŤ¶ĀÁāĻ„āí„Āĺ„Ā®„āĀ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„āĆ„Ā†„ĀĎ„ĀĮŤ¶ö„Āą„Ā¶„Āä„Āć„Āĺ„Āó„āá„ĀÜÔľĀ
- „āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āįŚ†ĪťÖ¨„ĀĮ„ÄĀŚŹó„ĀĎŚŹĖ„Ā£„ĀüśôāÁāĻ„Āģśôāšĺ°„ĀßťõĎśČÄŚĺó„Ā®„Āó„Ā¶Ť™≤Á®é„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äāśó•śú¨ŚÜÜ„Āł„ĀģśŹõťáĎ„ĀĮÁĄ°ťĖĘšŅā„Āß„Āô„Äā
- „É™„ā≠„ÉÉ„ÉČ„āĻ„ÉÜ„Éľ„ā≠„É≥„āįÁ≠Č„ĀģDeFiŚŹĖŚľē„āāŤ™≤Á®éŚĮĺŤĪ°„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀś®©Śą©ÁĘļŚģö„āŅ„ā§„Éü„É≥„āį„āĄśôāšĺ°„Āģśä䜏°„ĀĆťĚ쌳ł„ĀęŚõįťõ£„Āß„Āô„Äā
- ÁĒ≥ŚĎäśľŹ„āĆ„ĀĆÁôļŤ¶ö„Āô„āč„Ā®„ÄĀťáć„ĀĄŤŅĹŚĺīŤ™≤Á®é„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„āč„É™„āĻ„āĮ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚõĹÁ®éŚļĀ„ĀĮśĶ∑Ś§ĖŚŹĖŚľē„āāÁõ£Ť¶Ė„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
- Ś†ĪťÖ¨„Ā®„Āó„Ā¶Śĺó„ĀüśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£„āíŚ£≤Śćī„Āô„āč„Ā®„ÄĀ„ÄĆŚ£≤Śćīšĺ°ś†ľ„Äć„Ā®„ÄĆŚŹóŚŹĖśôā„Āģśôāšĺ°ÔľąŚŹĖŚĺóšĺ°ť°ćԾȄÄć„ĀģŚ∑ģť°ć„ĀĆŤ™≤Á®éŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
- śó•„ÄÖ„Āģś≠£ÁĘļ„Ā™śôāšĺ°Áģ°ÁźÜ„Ā®śźćÁõ䍮ąÁģó„ĀĮŚŅÖť†ą„Āß„Āô„ÄāÁĘļŚģöÁĒ≥ŚĎä„Āģťöõ„Āę„ĀĮšŅ°ť†ľ„Āß„Āć„āčśźćÁõ䍮ąÁģó„ÉĄ„Éľ„Éę„ĀģśīĽÁĒ®„ā팾∑„ĀŹśé®Ś•®„Āó„Āĺ„Āô„Äā

„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõ£šŅģŤÄÖ
śĚĎšłä Ť£ēšłÄÔľąŚÖ¨Ť™ćšľöŤ®ąŚ£ę„ÉĽÁ®éÁźÜŚ£ęÔľČ
ŚÖ¨Ť™ćšľöŤ®ąŚ£ęŤ©¶ť®ďŚźąś†ľŚĺĆ„ÄĀŚ§ßśČčÁõ£śüĽś≥ēšļļ„ÄĀ„É°„Éľ„āę„ÉľÁĶĆÁźÜŤ≤°Śčô„ÄĀšľöŤ®ąšļčŚčôśČÄ„āíÁĶĆ„Ā¶Áč¨ÁęčťĖčś•≠„ÄāšĽģśÉ≥ťÄöŤ≤®„ÉĽNFT„ÉĽ„ÉĖ„É≠„ÉÉ„āĮ„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ā≤„Éľ„Ɇ„āíŚįāťĖÄ„Ā®„Āô„āčÁ®éÁźÜŚ£ę„Ā®„Āó„Ā¶śīĽŤļć„ÄāŤá™„āČ„āāSTEPN„Ā™„Ā©„Āģ„ÉĖ„É≠„ÉÉ„āĮ„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ā≤„Éľ„Ɇ„Ā™„Ā©„āí„Éó„ɨ„ā§„Āó„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„ĀģśäēŤ≥áŚģ∂„ĀģÁ®éŚčô„āíśĒĮśŹī„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā
ūüí° „Āď„Ā°„āČ„āā„Āā„āŹ„Āõ„Ā¶Ť™≠„ĀŅ„Āü„ĀĄ
„Äź2025ŚĻīÁČą„ÄĎšĽģśÉ≥ťÄöŤ≤®„ĀģÁ®éťáĎŚģĆŚÖ®„ā¨„ā§„ÉČÔĹúŤ®ąÁģóśĖĻś≥ē„Ā®ÁĮÄÁ®é„ÉĀ„āß„ÉÉ„āĮ„É™„āĻ„Éą
‚ÄĽśú¨Ť®ėšļč„ĀĮAIÔľąšļļŚ∑•Áü•ŤÉĹԾȄāíśīĽÁĒ®„Āó„Ā¶Ťá™ŚčēÁĒüśąź„Āē„āĆ„ĀüŚÜÖŚģĻ„ā팟ę„āď„Āß„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤ®ėŤľČŚÜÖŚģĻ„Āģś≠£ÁĘļśÄß„āĄśúÄśĖįśÄß„Āę„ĀĮťÖćśÖģ„Āó„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀŚŅÖ„Āö„Āó„āāŚģĆŚÖ®śÄß„āíšŅĚŤ®ľ„Āô„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äāťá捶Ā„Ā™Śą§śĖ≠„Āģťöõ„ĀĮ„ÄĀŚÖ¨ŚľŹśÉÖŚ†Ī„āĄŚįāťĖÄŚģ∂„ĀģÁĘļŤ™ć„āā„Āā„āŹ„Āõ„Ā¶„ĀĒŚŹāÁÖß„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀĮŚŹāŤÄÉ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„ĀčÔľü
ťĖĘťÄ£Ť®ėšļč
- ŚĹďÁ§ĺ„ĀĮ„ÄĀśŹźšĺõ„Āô„āčśÉÖŚ†Ī„Āģś≠£ÁĘļśÄß„Ā®šŅ°ť†ľśÄß„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āč„āą„Ā܌䙄āĀ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„Āģ„ÄĀťĀ©śôāśÄß„ÄĀťĀ©ŚąáśÄß„Āĺ„Āü„ĀĮŚģĆŚÖ®śÄß„āíšŅĚŤ®ľ„Āô„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀšłćś≠£ÁĘļ„Āĺ„Āü„ĀĮšłćšĹúÁāļÔľąšłćś≥ēŤ°ĆÁāļ„Āĺ„Āü„ĀĮŚ•ĎÁīĄ„ĀĚ„ĀģšĽĖԾȄĀč„āČÁĒü„Āė„āč„ĀĄ„Āč„Ā™„ā蜟挧Ī„Āĺ„Āü„ĀĮśźćŚģ≥„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„āāŤ≤¨šĽĽ„āíŤ≤†„ĀĄ„Āĺ„Āõ„āď„Äā
- ŚĹďÁ§ĺ„ĀĆśŹźšĺõ„Āô„āč„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄÔľąšĽ•šłč„ÄĀ„ÄĆśú¨„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀĄ„Āĺ„ĀôԾȄĀĮ„Āā„ĀŹ„Āĺ„Āß„āāŚÄčšļļ„Āł„ĀģśÉÖŚ†Ī„ĀģśŹźšĺõ„āíÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„Āā„āä„ÄĀŚēÜÁĒ®ÁõģÁöĄ„Āģ„Āü„āĀ„Ā꜏źšĺõ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀśäēŤ≥áśīĽŚčē„āíŚčߍ™ėŚŹą„ĀĮŤ™ėŚľē„Āô„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀŚŹĖŚľēŚŹą„ĀĮŚ£≤Ť≤∑„ā퍰ƄĀÜťöõ„ĀģśĄŹśÄĚśĪļŚģö„ĀģÁõģÁöĄ„ĀßšĹŅÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮťĀ©Śąá„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äāśú¨„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„ĀĮśäēŤ≥áŚä©Ť®Ä„Ā®„Ā™„āčśäēŤ≥á„ÄĀÁ®éťáĎ„ÄĀś≥ēŚĺčÁ≠Č„Āģ„ĀĄ„Āč„Ā™„āčŚä©Ť®Ä„āāśŹźšĺõ„Āõ„Āö„ÄĀ„Āĺ„Āü„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģťáĎŤěć„ĀģŚÄ茹•ťäėśüĄ„ÄĀťáĎŤěćśäēŤ≥á„Āā„āč„ĀĄ„ĀĮťáĎŤěćŚēÜŚďĀ„ĀęťĖĘ„Āô„āč„ĀĄ„Āč„Ā™„āčŚčߌĎä„āā„Āó„Āĺ„Āõ„āď„Äāśú¨„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„ĀģšĹŅÁĒ®„ĀĮ„ÄĀŤ≥ᜆľ„Āģ„Āā„āčśäēŤ≥áŚįāťĖÄŚģ∂„ĀģśäēŤ≥áŚä©Ť®Ä„ĀꌏĖ„Ā£„Ā¶šĽ£„āŹ„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā
- śú¨„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„ĀĮśôāťĖď„ĀģÁĶĆťĀé„Āę„āą„āäšłćś≠£ÁĘļ„Ā®„Ā™„ā茆īŚźą„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀŚĺď„Ā£„Ā¶„Éí„āĻ„Éą„É™„āę„ÉęśÉÖŚ†Ī„Ā®„Āó„Ā¶„Āģ„ĀŅŤß£ťáą„Āē„āĆ„āč„ĀĻ„Āć„Āß„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚĹďÁ§ĺ„āāÁ¨¨šłČŤÄÖ„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„ÉĽ„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄ„Éľ„āā„ÄĀśėéÁ§ļŚŹą„ĀĮťĽôÁ§ļ„āíŚēŹ„āŹ„Āö„ÄĀśŹźšĺõ„Āē„āĆ„Āüśú¨„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„Āģś≠£ÁĘļśÄߌŹą„ĀĮÁõģÁöĄťĀ©ŚźąśÄß„ĀęťĖĘ„Āô„āčšŅĚŤ®ľ„āí„Āô„ĀĻ„Ā¶śėéÁ§ļÁöĄ„Āęśéíťô§„Āó„ÄĀśú¨„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„ĀģŤ™§Ť¨¨„ÉĽšłćś≠£ÁĘļ„āĄťĀÖŚĽ∂„ÄĀŚŹą„ĀĮ„ĀĚ„āĆ„āČ„Āęšĺ̜膄Āó„Ā¶„Ā™„Āē„āĆ„ĀüŤ°ĆÁāļ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀšĹē„āČ„ĀģŤ≤¨šĽĽ„āāŤ≤†„ĀÜ„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā
- śú¨„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„Āč„āČšĽĖ„Āģ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„Āł„Āģ„É™„É≥„āĮ„Āĺ„Āü„ĀĮšĽĖ„Āģ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„Āč„āČŚĹďÁ§ĺ„Āģ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„Āł„Āģ„É™„É≥„āĮ„ĀĆśŹźšĺõ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„ā茆īŚźą„Āß„āā„ÄĀŚĹďÁ§ĺ„ĀĮ„ÄĀŚĹďÁ§ĺ„Āģ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„ÉąšĽ•Ś§Ė„Āģ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„Āä„āą„Ā≥„ĀĚ„Āď„Āč„āČŚĺó„āČ„āĆ„āčśÉÖŚ†Ī„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶Ś¶āšĹē„Ā™„āčÁźÜÁĒĪ„ĀęŚüļ„Ā•„ĀĄ„Ā¶„āāšłÄŚąá„ĀģŤ≤¨šĽĽ„āíŤ≤†„āŹ„Ā™„ĀĄ„āā„Āģ„Ā®„Āó„Āĺ„Āô„Äā
- śú¨„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„Āę„ĀĮšĹúśąźŤÄÖ„ĀģŚąÜśěźŚŹä„Ā≥śĄŹŤ¶č„ĀĆŚźę„Āĺ„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Āā„ĀŹ„Āĺ„Āß„āāšĹúśąźŤÄÖ„ĀģŤ¶čŤß£„Āß„Āā„āä„ÄĀŚĹďÁ§ĺ„ĀģŤ¶čŤß£„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā
šĽ•šłä
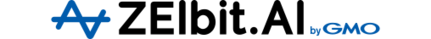



„ā≥„É°„É≥„Éą 0šĽ∂