【2025年最新】仮想通貨の贈与は税金に注意!贈与税・みなし譲渡所得の計算から申告方法まで完全ガイド
※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
この記事のポイント
最近、保有しているビットコインの価値がかなり上がったんだ。そろそろ子供に一部を譲ってあげたいんだけど、こういう場合、税金ってかかるのかな?
素晴らしいですね!ただ、仮想通貨の贈与には注意が必要です。実は、資産を受け取るお子さんだけでなく、贈与するあなた自身にも税金がかかる可能性があるんです。これは「みなし譲渡」という制度が関係しています。
えっ、あげる側にも税金が!?それは知らなかった…。詳しく教えてほしい!
■ 仮想通貨の贈与にかかる税金とは?2つの納税義務を理解しよう
仮想通貨の贈与で最も重要なポイントは、一つの贈与行為が「渡した側」と「受け取った側」の双方に、それぞれ異なる納税義務を発生させる可能性があるという点です。 この事実を知らないと、後から予期せぬ高額な税金に驚くことになりかねません。
- 受け取った側(受贈者): 贈与された仮想通貨の価値に対して贈与税が課される可能性があります。
- 渡した側(贈与者): 贈与した時点での含み益(購入時からの値上がり益)に対して所得税が課される可能性があります。 これは「みなし譲渡所得」と呼ばれ、税法上、時価で売却したものとみなされるためです。
特に、渡した側にかかる「みなし譲渡所得税」は見落とされがちです。価値が上がった資産を贈与する行為は、「その資産を時価で売却し、得られた現金を渡した」と解釈されるのです。 この仕組みを理解することが、仮想通貨の贈与を考える上での第一歩となります。
■ 【貰う側】贈与税の仕組みと計算方法
まず、仮想通貨を受け取った側(受贈者)にかかる贈与税について見ていきましょう。納税義務者は、資産を受け取った受贈者本人です。
年間110万円の基礎控除(暦年贈与)
贈与税には、受贈者一人あたり年間110万円の基礎控除が設けられています。 その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。 これには仮想通貨だけでなく、現金など他の資産からの贈与も含まれる点に注意しましょう。
贈与財産の評価方法
贈与税の計算に使われる仮想通貨の価値は、贈与が行われた瞬間の「時価」です。 一般的には、仮想通貨交換業者が公表している取引価格を時価とします。 複数の取引所に上場している場合は、贈与時点で最も低い価格を公表している取引所の価格を選択することが認められています。
贈与税の計算例
贈与税額は、年間に贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、残った金額に税率を掛けて計算します。 税率には、親子間・祖父母から孫への贈与などで適用される有利な「特例税率」と、それ以外の「一般税率」があります。
【例】25歳のAさんが、父親から時価500万円のビットコインを贈与された場合(他に贈与はない)
- 課税価格:500万円 – 110万円(基礎控除) = 390万円
- 税額計算(特例税率):390万円 × 15% – 10万円(速算控除額) = 48万5,000円
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
■ 【渡す側】要注意!「みなし譲渡所得」という隠れた税金
ここからが、多くの人が見落としがちな「渡した側(贈与者)」の税金です。価値が上がった仮想通貨を個人に贈与すると、その時点の時価で売却(譲渡)したとみなされ、取得価額との差額(利益)に対して所得税が課されます。 これが「みなし譲渡所得」です。
所得の計算方法
計算式は「贈与時の時価 − 取得価額」です。
【例】1BTCを100万円で購入したBさんが、時価500万円になった時点で子供に贈与した場合
- みなし譲渡所得:500万円(時価) − 100万円(取得価額) = 400万円
この400万円がBさんの所得として、所得税の課税対象となります。
最大の罠「雑所得」
このみなし譲渡所得は、原則として「雑所得」に分類されます。 これが仮想通貨の税務における大きなデメリットの一つです。
- 高い累進税率: 給与所得など他の所得と合算され、所得税・住民税を合わせて最高約55%の税率が適用されます。
- 損益通算の禁止: 仮想通貨の損失を、給与所得など他の所得の利益と相殺することはできません。
- 繰越控除の禁止: その年に出た損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺することもできません。
株式投資の利益が約20%の申告分離課税であることと比べると、仮想通貨の税制がいかに投資家にとって不利であるかがわかります。この不利な税制が、贈与者にとって想定外の重い負担を生む最大の要因です。

AIでかんたん確定申告
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する暗号資産のAI損益計算サービスです。安心・かんたん・使いやすいサービスで、毎年の申告をスムーズに。
公式サイトで詳しく見る■ 仮想通貨の「贈与」と「相続」、どっちが得?税金負担を徹底比較
資産承継の方法として「贈与」と「相続」がありますが、仮想通貨の場合、この選択は非常に重要です。 現行制度では、相続が極めて不利になる「二重課税」のリスクがあるためです。
相続の重大な問題点
- 相続税と所得税の二重課税: 相続人は、まず相続した仮想通貨の価値に対して相続税を支払います。その後、その仮想通貨を売却して利益が出た場合、その利益に対してさらに所得税(雑所得)を支払う必要があります。
- 取得費加算の特例が使えない: 土地や株式などを相続した場合、支払った相続税の一部を売却時の経費にできる「取得費加算の特例」という有利な制度があります。しかし、仮想通貨の売却益は「雑所得」であるため、この特例の対象外です。
この結果、被相続人が安く買った仮想通貨が高騰していた場合、相続税と売却時の所得税を合わせると、税率が100%を超えて手取りがマイナスになるという事態さえ起こり得ます。
戦略的分析:贈与が有利になるケース
上記の二重課税リスクを避けるため、生前に計画的な「贈与」を行うことが有効な対策となる場合があります。 贈与者には「みなし譲渡所得税」がかかりますが、受贈者の取得価額は贈与時の時価にリセットされます。これにより、将来受贈者が売却する際の所得税負担をコントロールし、家族全体でのトータルの税負担を低減できる可能性があります。
最も確実な対策の一つは、保有者自身が生前に売却して一度所得税を確定させ、残った現金を贈与または相続させることです。
■ 仮想通貨贈与の必須手続きと申告方法
税務リスクを避けるためには、適切な手続きと記録管理が不可欠です。
- 贈与契約書の作成: 「いつ、誰が、誰に、何を、いくらで贈与したか」を客観的に証明するため、贈与契約書を必ず作成しましょう。 これは税務調査の際にあなたを守る最も重要な書類です。契約日、当事者の氏名・住所、仮想通貨の銘柄・数量、贈与の実行日などを明記します。
- 確定申告: 贈与税も所得税も、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用したe-Taxでの申告が便利です。
- 贈与税(受贈者): 「財産の明細」欄に、種類「暗号資産」、細目「ビットコイン」などと記載し、贈与時の時価を記入します。
- 所得税(贈与者): 「雑所得」の「その他」として、「収入金額」に贈与時の時価、「必要経費」に取得価額を記入します。
- 記録の保管: 贈与税の時効は原則6年(悪質な場合は7年)です。 トラブルを避けるため、贈与契約書、取引所の取引履歴、贈与時の時価の証拠(スクリーンショット等)、申告書の控えなどは最低7年間は保管しましょう。
■ 申告漏れはバレる?重いペナルティと税務署の調査
「仮想通貨の取引は匿名だからバレない」というのは、もはや通用しない危険な考えです。税務当局は様々な方法で取引を把握しています。
- 交換業者の報告義務: 国内の交換業者は、顧客の年間取引報告書を税務当局に提出しています。
- トラベル・ルール: 交換業者間の送金では、送金者と受取人の情報が共有・保存されるルールが導入されています。
- 国際的な情報交換(CRS): 海外の取引所の口座情報も、日本の税務当局に共有される仕組みがあります。
申告漏れが発覚した場合、本来の税金に加え、厳しいペナルティが課せられます。
| 種類 | 課税条件 | 税率 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった | 15%~30% (自主申告なら5%) |
| 過少申告加算税 | 申告額が本来より少なかった | 10%~15% |
| 重加算税 | 意図的な隠蔽など悪質なケース | 35%~40% |
| 延滞税 | 法定納期限に遅れて納付した | 利息に相当する税金(年率 約2.4%~8.7% ※令和6年) |
■ よくある質問(Q&A)
Q. 年間の贈与額が110万円以下なら、本当に何もしなくて大丈夫ですか?
A. はい、その年の贈与総額が110万円以下であれば、贈与税の申告は不要です。 ただし、将来の税務調査に備えて、誰からいつ、いくらの仮想通貨を贈与されたかの証拠として、たとえ少額でも贈与契約書を作成し、取引記録と共に保管しておくことを強くお勧めします。
Q. 海外の取引所を使ったり、個人ウォレット間で直接送ったりすればバレませんか?
A. そのような考えは非常に危険です。税務当局は共通報告基準(CRS)により各国の金融口座情報を交換しており、海外口座も把握されやすくなっています。 また、ブロックチェーン上の取引記録は誰でも追跡可能です。 最終的に日本円に換金する際には国内の取引所を経由することが多く、その段階で過去の取引が発覚する可能性も高いです。
Q. 「みなし譲渡」の税金が高すぎて払えそうにありません。何か良い方法はありますか?
A. 含み益が大きい場合、贈与者にかかる所得税は確かに高額になりがちです。対策としては、一度に全額を贈与するのではなく、暦年贈与の非課税枠(110万円)を使って数年に分けて贈与する方法があります。 あるいは、贈与者自身が必要な分だけを売却して納税資金を確保し、残りを贈与・相続するという計画も考えられます。どのような方法が最適かは個々の状況によるため、必ず事前に暗号資産に詳しい税理士に相談してください。
【今日の気づき】仮想通貨贈与の税金対策 まとめ
仮想通貨の贈与は、単純な資産の移動ではありません。計画を誤ると、資産価値の大半を税金で失いかねない重大なリスクをはらんでいます。
- 二重の納税義務を忘れない: 贈与は「もらう側の贈与税」だけでなく、「あげる側の所得税(みなし譲渡)」の両方を考慮する必要があります。
- 「みなし譲渡」が最大の関門: 含み益に対する所得税は、最高約55%の「雑所得」として課税され、非常に重い負担となります。
- 記録が身を守る: 贈与契約書と取引記録は、税務調査に対する最強の防御策です。必ず作成・保管しましょう。
- 専門家への相談は必須: 110万円を超える贈与、特に含み益の大きい仮想通貨を贈与する場合は、自己判断は禁物です。 必ず実行前に、暗号資産に精通した税理士に相談し、最適なプランを立てることが、あなたの資産を守るための最も賢明な選択です。
💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
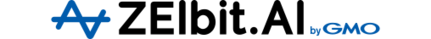
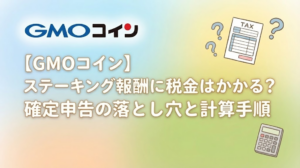


コメント 0件