仮想通貨の送金で税金はかかる?【2025年最新】課税・非課税の全パターンと確定申告を解説
※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
最近、海外の取引所にあるイーサリアムを日本の自分の口座に移したんだけど、これって税金がかかるのかな?あと、友人に少しだけビットコインを送ってあげたんだけど、これも申告が必要?
とても良い質問ですね。仮想通貨の「送金」は、多くの方が税金の判断に迷うポイントです。実は、送金の目的によって課税対象になるケースとならないケースが明確に分かれています。今日はその違いを、具体的なパターンを交えながら分かりやすく解説していきますね。
この記事の要点
仮想通貨の送金と税金の基本ルール|総合課税と雑所得
まず大前提として、個人が仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。 これは給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となります。
総合課税は、所得の合計額が大きくなるほど税率が上がる「累進課税」が適用されるため、所得税と住民税を合わせると最大で約55%もの税金がかかる可能性があります。 これは、利益に対して一律約20%の税率が適用される株式投資やFX(申告分離課税)との大きな違いです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
【パターン別】仮想通貨の送金で税金がかからないケース vs かかるケース
それでは本題の「送金」についてです。税金がかかるかどうかは、その送金が「利益確定」を伴うかどうかで決まります。
税金がかからない送金:単なる「資産の移動」
以下のケースは、実質的な所有者が変わらず、利益も確定していないため、単なる資産の保管場所の移動とみなされ非課税となります。
- 国内の取引所Aから、自分の取引所Bへ送金する
- 取引所から、自分が管理する個人ウォレット(MetaMaskなど)へ送金する
- 自分が利用する海外取引所(Binanceなど)から、国内の自分の取引所へ送金する
税金がかかる送金:「利益確定」とみなされる取引
一方で、送金によって実質的な価値の交換が行われる場合は「利益確定」とみなされ、課税対象となります。 つまり、含み益のある仮想通貨が、その価値を実現する形で手元から離れた瞬間に課税イベントが発生します。
- 商品やサービスの対価として送金する(決済)
保有する仮想通貨をその時点の時価で売却し、日本円で商品を買ったのと同じ扱い(みなし売却)になります。 - 他の種類の仮想通貨と交換するために送金する
ビットコイン(BTC)を送ってイーサリアム(ETH)を受け取る場合、BTCを売却して利益を確定させ、その資金でETHを購入したとみなされます。 - 第三者に日本円などで売却するために送金する
友人や知人との間でも、対価を受け取る個人間売買は明確な売却行為であり、課税対象です。 - 第三者に無償で送金する(贈与)
これは非常に特殊なケースで、送った側(贈与者)に「みなし譲渡所得」として課税される可能性があります。詳しくは次章で解説します。
要注意!仮想通貨の贈与・個人間売買の「みなし譲渡」という罠
えっ、無償であげただけなのに、送った側に税金がかかるんですか?
その通りです。ここが仮想通貨の税務で最も誤解されやすいポイントの一つ、「みなし譲渡所得」の考え方です。含み益のある資産を無償で贈与した場合、「贈与した時点の時価で売却した」とみなして、送った人が利益を計算し、納税する必要があるのです。
例えば、1BTCを100万円で購入した人が、時価700万円になった時点で子供に1BTCを贈与したとします。この場合、贈与した親は、差額の600万円(700万円 – 100万円)が利益として実現したとみなされ、自身の雑所得として確定申告をしなければなりません。
さらに、受け取った子供側も、贈与された仮想通貨の価値(この場合は700万円)が贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超えていれば、贈与税の申告・納税が必要になります。 このように、一つの贈与行為が、所得税と贈与税という二重の課税を生む可能性があるため、家族間での送金には特に注意が必要です。
仮想通貨の損益計算方法と確定申告の進め方
課税対象となる取引を把握したら、次は正確な利益を計算する必要があります。取引所が複数にまたがったり、DeFiやNFTの取引があったりすると、手計算は非常に複雑で間違いやすくなります。
計算方法の選択:移動平均法 vs 総平均法
取得価額の計算方法は、国税庁により「移動平均法」と「総平均法」の2つが認められています。
- 移動平均法: 仮想通貨を購入するたびに、その時点での平均取得単価を再計算する方法。計算は複雑ですが、取引ごとの損益を正確に把握できます。
- 総平均法: 1年間の購入総額を、購入総数量で割って年間の平均取得単価を算出する方法。計算はシンプルですが、期中の正確な損益は年末まで分かりません。
一度選択した計算方法は、原則として継続して使用する必要があり、変更するには税務署への事前届出が必要です。

複雑な損益計算はAIにおまかせ
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する暗号資産のAI損益計算サービスです。DeFiや海外取引所の取引履歴にも対応し、安心・かんたん・使いやすいサービスで毎年の確定申告をスムーズに。
公式サイトで詳しく見る必要経費に計上できるもの
仮想通貨の利益(所得)は、収入から必要経費を差し引いて計算します。認められる可能性がある経費には以下のようなものがあります。 経費計上には、その支払いを証明する領収書などの保管が必須です。
- 取引所やウォレットで支払った取引手数料・送金手数料
- Gtax、Cryptact、ZEIbit.AIなどの損益計算ツールの利用料
- 取引に使用したパソコンの購入費用(10万円以上は減価償却)
- インターネット回線やスマートフォンの通信費(家事按分が必要)
- 仮想通貨投資に関する書籍代やセミナー参加費
よくある質問(Q&A)
海外取引所の利益なら、日本の税務署にはバレないって聞きましたけど本当ですか?
それは非常に危険な誤解です。日本の居住者は、国内外どこで得た利益であっても申告義務があります。 国税庁はCRS(共通報告基準)という制度で各国の金融口座情報を自動的に入手したり、租税条約に基づいて情報照会を行ったりできます。 海外での利益も必ず申告してください。
会社員で、年間の利益が20万円以下なら何もしなくていいんですよね?
惜しいですね!年20万円以下の利益の場合、所得税の確定申告は不要になりますが、それはあくまで国税の話です。 地方税である住民税の申告義務は残ります。 何もしないと住民税の申告漏れとなり、後から追徴課税される可能性があるので、市区町村への申告が必要です。
今年、仮想通貨で大きな損失が出てしまったんですが、給料から天引きされる税金を減らせますか?
残念ながら、それはできません。仮想通貨の利益は「雑所得」に分類されるため、同じ雑所得内の他の利益とは相殺できますが、給与所得や事業所得など、他の所得区分の利益と損失を相殺(損益通算)することは認められていません。 また、損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」もできません。
今日の気づき:仮想通貨「送金」の税金対策まとめ
- 資産移動は非課税: 自分の取引所口座間や個人ウォレットへの送金は、利益が確定しないため税金はかかりません。
- 価値の交換は課税対象: 商品購入、他の仮想通貨との交換、第三者への売却など、経済的価値と交換する送金は「利益確定」とみなされ課税されます。
- 贈与の罠に注意: 含み益のある仮想通貨を贈与すると、送った側に「みなし譲渡所得」として所得税が課される可能性があります。
- 記録こそが最強の防御: 全ての取引日時、数量、時価を正確に記録することが、適切な納税と税務調査への備えとなります。
💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
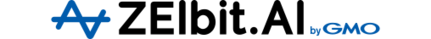
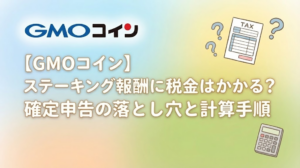


コメント 0件