仮想通貨の税金、税務署に相談は損?税理士との違いと選び方を解説
※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
最近、仮想通貨で利益が出たんだけど、税金のことがさっぱり分からなくて…。計算も複雑そうだし、税務署に行けば丁寧に教えてもらえるのかな?
良い質問ですね。仮想通貨の税金は複雑なので、誰に相談するかは非常に重要です。実は「税務署」と「税理士」では、できることや役割が全く違うんですよ。今回は、あなたの状況に合わせて最適な相談先を選べるように、その違いを分かりやすく解説していきますね。
この記事のポイント
仮想通貨の税金相談:税務署と税理士の根本的な違い
仮想通貨の税金について疑問が生じたとき、主な相談先は「税務署」と「税理士」の2つです。しかし、この2つは提供するサービスや立場が根本的に異なります。この違いを理解することが、問題解決への第一歩です。
端的に言えば、税務署は「中立な立場で税金のルールを教える審判」のような存在であり、税理士は「あなたの利益を最大化するために戦うコーチ」のような存在です。どちらが良いというわけではなく、あなたの状況や目的によって選ぶべき相手が変わります。
| 項目 | 税務署 | 税理士 |
|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 有料(5万円~数十万円) |
| 相談範囲 | 税法の一般的解釈、手続き案内 | 計算代行、申告代理、税務戦略全般 |
| 節税アドバイス | 不可(中立的な立場) | 可能(納税者の代理人として) |
| 計算代行 | 不可 | 可能 |
| 仮想通貨の専門性 | 担当者による(保証なし) | 専門家を選べる(保証あり) |
| 税務調査対応 | 不可(調査する側) | 可能(代理人として立ち会い) |
| 最適な人 | ・取引がシンプルで利益が少額な人 ・自分で計算できるが手続きを確認したい人 |
・取引が複雑、利益が大きい人 ・事業所得を検討している人 ・安心を買いたい人 |
【選択肢A】税務署への相談ガイド
税務署は、国税に関する行政機関として、納税者が正しく申告・納税するためのサポートを提供しています。自分で申告作業を進められる人が、手続きやルールの最終確認をするのに適しています。
税務署ができること・できないこと
- できること:税法の一般的なルールや解釈の質問、確定申告書の書き方指導、手続きの案内などです。例えば、「仮想通貨の利益は何所得ですか?」といった基本的な質問には明確に答えてくれます。
- できないこと:個別の取引履歴を基にした損益計算の代行や、納税者にとって最も有利になるような具体的な節税アドバイス(タックスプランニング)は行いません。あくまで中立的な立場での情報提供がメインです。
相談のメリット・デメリット
最大のメリットは、何と言っても無料で相談できる点です。国が定めるルールに関する最も正確で権威ある回答を得ることができます。
一方、デメリットは、相談時間が平日の日中に限られること、そして職員が必ずしもDeFiやNFTといった最新の仮想通貨取引に精通しているとは限らないことです。また、税務署の目的は「適正な課税の確保」であり、あなたの節税を積極的に手伝ってはくれません。
相談に行く際は、事前に質問をまとめ、年間取引報告書などの関連資料をすべて揃えておくことが、限られた時間を有効に使うために不可欠です。対面相談は事前予約が必須で、国税庁のLINE公式アカウントからも予約が可能です。
【選択肢B】税理士への依頼ガイド
税理士は、税務に関する専門的なサービスを提供する国家資格者です。納税者の代理人として、複雑な計算から節税戦略まで、幅広くサポートしてくれます。
なるほど、立場が全然違うんだね。僕は取引回数も多いし、DeFiも少し触ったから税理士さんの方が良さそうかな…。でも、そもそも自分の利益が『事業所得』になるのか『雑所得』になるのかもよく分かってないんだ。
そこが非常に重要なポイントです!所得区分によって納税額が大きく変わる可能性があるんですよ。特に『事業所得』として認められるかどうかは、大きな分かれ道になります。その違いを詳しく見ていきましょう。
税理士に依頼すべきケース
以下のようなケースでは、税理士への依頼が有力な選択肢となります。
- 取引件数が非常に多い、または複数の国内外取引所を利用している
- DeFi、NFT、レンディングなど、複雑な取引を行っている
- 仮想通貨で多額の利益(数百万円以上)が出ている
- 節税効果の高い「事業所得」での申告を検討している
- 本業が忙しく、確定申告に時間と手間をかけたくない
依頼のメリット・デメリット
最大のメリットは、煩雑な損益計算から申告書の作成・提出までを全て代行してもらえる手軽さと、専門家による正確な申告がもたらす安心感です。それに加えて、含み損の確定(損出し)など、合法的な範囲での戦略的な節税アドバイスを受けられることも大きな利点です。万が一の税務調査の際も、代理人として専門的な対応を任せられます。
デメリットは費用がかかる点です。料金は取引の複雑さによって変動し、シンプルな申告で5万円~10万円、DeFiなどを含む複雑なケースでは20万円以上になることもあります。重要なのは、「仮想通貨に強い」実績豊富な税理士を選ぶことです。多くの事務所が提供する無料相談を活用し、専門性や相性を見極めましょう。
所得区分が重要!雑所得と事業所得の違いと節税効果
仮想通貨の利益は、原則として「雑所得」に分類されます。これは給与所得など他の所得と合算して税額が決まる「総合課税」の対象です。雑所得の大きなデメリットは、仮想通貨取引で損失が出ても、給与所得など他の黒字の所得と相殺(損益通算)ができない点です。
しかし、一定の要件を満たす場合は「事業所得」として申告できる可能性があります。
- その年の仮想通貨取引による収入金額が300万円を超えること
- その取引に関する帳簿書類を保存していること
ここで注意すべきは、要件が「利益」ではなく「収入(売却額の総額)」である点です。事業所得の最大のメリットは、損失を他の所得と損益通算できることや、青色申告による最大65万円の特別控除など、大きな節税効果が期待できる点です。ただし、要件を満たしても、最終的に事業として認められるかは税務署の判断次第であり、特に副業の場合は否認されるリスクも伴います。この判断が、専門家への相談価値を高める大きな要因となっています。

AIでかんたん確定申告
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する暗号資産のAI損益計算サービスです。安心・かんたん・使いやすいサービスで、毎年の申告をスムーズに。
公式サイトで詳しく見る要注意!仮想通貨で税金が発生する6つのタイミング
「日本円に換金しなければ税金はかからない」という考えは、申告漏れに繋がる危険な誤解です。税金が発生する(=利益が確定する)タイミングは、思った以上に多く存在します。
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 法定通貨への売却 | 保有する仮想通貨を日本円や米ドルに売却した時点で、売却価格と取得価額の差額が利益として認識されます。 |
| 他の仮想通貨との交換 | ビットコインでイーサリアムを買うなど、仮想通貨同士を交換した時点で、元々保有していた通貨を時価で売却したと見なされ、課税対象となります。 |
| 商品やサービスの購入 | 仮想通貨で決済した場合も、その仮想通貨を一度時価で売却し、商品を購入したと見なされて課税されます。[cite: 3] |
| マイニングによる取得 | マイニングによって新たに仮想通貨を取得した場合、その取得時点での時価が収入となります。PC設備費や電気代は経費として計上可能です。 |
| ステーキング・レンディング報酬 | 保有・提供することで得られる報酬や利子も、受け取った時点の時価で所得として認識されます。[cite: 9, 39] |
| 無償での取得(エアドロップ等) | キャンペーンやプロジェクトからの無償配布(エアドロップ)で仮想通貨を取得した場合も、原則として取得時点の時価で所得となります。 |
専門家が回答!仮想通貨の税金に関するよくある質問(Q&A)
利益が20万円以下なら確定申告しなくていいって聞いたけど、本当?
それは半分正解で、半分は間違いです。給与所得者の場合、仮想通貨などの所得が年間20万円以下なら「所得税」の確定申告は不要になることがあります。しかし、これはあくまで国税の話。地方税である「住民税」の申告義務は免除されないため、利益が1円でもあれば原則として市区町村への申告が必要です。この「20万円ルール」は多くの人が陥りがちな罠なので注意が必要ですよ。最も簡単な解決策は、20万円以下でも所得税の確定申告をしてしまうことです。そうすれば住民税の申告も一度で済みます。
もし年間トータルでマイナスだったら、申告はしなくてもいいの?
それは所得区分によります。利益が「雑所得」の場合、損失を申告しても税金上のメリットはないので、申告義務はありません。しかし、もし「事業所得」として申告していて損失が出た場合は、必ず申告すべきです。申告すれば、損失を給与所得など他の所得と相殺(損益通算)したり、損失を翌年以降3年間繰り越したりして、将来の税金を減らせる可能性があります。
副業で仮想通貨をやってるんだけど、会社にバレたくないな…。
ご安心ください、対策はあります。会社に知られる主な原因は、住民税の金額が給与から天引き(特別徴収)される際に、副業所得の分だけ増額してしまうことです。これを避けるには、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」で、給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法として「自分で納付」(普通徴収)を選択します。これにより、仮想通貨の利益にかかる住民税の納付書は自宅に直接送付されるため、会社を経由せずに自分で納付することができます。
仮想通貨の税金について、税務署に相談するか、税理士に依頼するかは、単に無料か有料かの問題ではありません。取引の複雑さ、利益の大きさ、そして何より「申告ミスによる追徴課税のリスク」をどれだけ許容できるか、というリスク管理の視点で判断することが重要です。取引がシンプルなら税務署で十分ですが、利益が大きくなるほど、専門家である税理士に依頼する価値は高まります。税理士費用は、安心と正確性を手に入れるための「投資」と捉えましょう。
💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
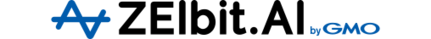
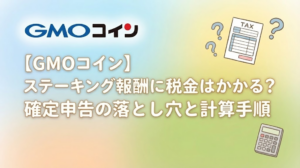


コメント 0件