【2025年版】仮想通貨の税金完全ガイド|計算方法と節税チェックリスト
※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
年末が近づいてきました…!今年、暗号資産で予想以上の利益が出たのですが、税金が最大55%にもなると聞いて、正直どうしたらいいか分からず焦っています。今からでも間に合う、具体的な節税方法って何かありますか?
そのお悩み、非常によく分かります。ご安心ください。年末までの期間を有効活用すれば、賢く税負担を軽減することが可能です。暗号資産の税金は高いですが、計画的な対策が鍵となります。今日は、まずご自身の税率を正確に把握する方法から始め、具体的な節税テクニック、さらには大きな利益が出た方向けの上級テクニック「法人化」まで、順を追って徹底解説します!
この記事の目次
■ 最初のステップ:あなたの「限界税率」を知る
暗号資産の利益(所得税法上は多くの場合「雑所得」に分類)は、給与所得などの他の所得と合算した「課税所得」の合計額に対して税率が決まる「総合課税」の対象です。そして、所得が増えるほど税率も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
節税戦略を立てる上で最も重要なのは、ご自身の所得がどの税率区分に位置し、利益が1円増えた場合に何%の税金がかかるか、つまり「限界税率」を把握することです。まずは下の速算表で、ご自身の現在の所得状況がどこに当てはまるかを確認してみましょう。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 | 合計税率 (住民税10%込の目安) |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 | 約15% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | 約20% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 | 約30% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | 約33% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 約43% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | 約50% |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | 約55% |
※上記に加えて、各年の基準所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課されます。
■ 年末までに実践!プロが教える4つの節税テクニック
ご自身の税率を確認できたら、いよいよ具体的な節税アクションプランに移ります。今からでも十分に間に合う、効果的な4つのテクニックを詳しく見ていきましょう。
-
テクニック1:含み損の銘柄を売却して「損益通算」する
最も基本的かつ強力な節税策が、いわゆる「損出し」です。保有中の銘柄で含み損があるものを年内に売却し、損失を確定させます。この損失は、同年内の他の暗号資産取引で得た利益と相殺(損益通算)できます。例えば、+300万円の利益があっても、-100万円の損失を確定させれば、課税対象の利益は200万円に圧縮できます。暗号資産の損失は翌年に繰り越せないため、年内に必ず行いたい対策です。 -
テクニック2:必要経費を漏れなく計上する
暗号資産取引のために直接かかった費用は「必要経費」として利益から差し引けます。取引所手数料、関連書籍代、セミナー参加費、損益計算ツールの利用料はもちろん対象です。PCやスマホの購入費も、取引に使用した割合を合理的に説明できるなら家事按分して経費にできます(※10万円以上の資産は原則、減価償却での計上)。領収書は必ず保管しましょう。 -
テクニック3:利益確定のタイミングを年またぎで分散する
累進課税の仕組みを逆手に取った戦略です。年末時点で大きな含み益があり、全て利確すると税率区分が上がってしまう場合(例:課税所得が695万円や1,800万円の壁を超える)、一部の利益確定を翌年1月以降に持ち越すことを検討します。これにより、単年の所得が急増して高い税率が適用されるのを避け、複数年にわたって税負担を平準化できます。 -
テクニック4:iDeCoやふるさと納税など「所得控除」をフル活用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や、ふるさと納税の寄付金は、課税所得から直接差し引ける「所得控除」の対象です。これらは暗号資産の利益(雑所得)を直接減らすわけではありませんが、課税所得全体の金額を圧縮するため、結果的に所得税・住民税の総額を減らす効果があります。年末が申込期限のケースも多いので、まだ利用していない場合は積極的に検討しましょう。
■ 【上級編】年間利益800万円超なら検討したい「法人化」
もし給与所得と暗号資産の利益を合わせた年間所得が恒常的に800万円を超えるようなら、「法人化」を検討する価値が出てきます。個人の所得税が最大55%(住民税含む)なのに対し、法人税の実効税率は最大でも約34%程度。この税率の差を利用して、トータルの税負担を大きく軽減できる可能性があります。
- 法人化の主なメリット:
①税率の低減、②赤字を10年間繰り越せる「繰越欠損金」、③自分への役員報酬や退職金など経費計上できる範囲の拡大、④家族を役員にして所得を分散できる、⑤相続対策上有利になる場合がある。 - 法人化の主なデメリット:
①法人の設立・維持にコストがかかる(登記費用、税理士報酬など)、②赤字でも法人住民税の均等割(最低7万円)が発生する、③社会保険への加入義務、④事務負担の増大。
法人化は強力な選択肢ですが、デメリットも大きいため、個々の状況に合わせた慎重な判断が必要です。まずは信頼できる税理士に相談し、詳細なシミュレーションを依頼することをお勧めします。

複雑な損益計算もAIでかんたんに
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する暗号資産のAI損益計算サービスです。正確な損益把握は節税の第一歩。毎年の申告をスムーズにしませんか?
公式サイトで詳しく見る■ よくある質問(Q&A)
「損出し」のために売却した暗号資産、すぐに同じ価格で買い戻しても大丈夫なのでしょうか?
良い質問ですね。短時間での売買、いわゆる「ウォッシュセール」については、日本の税法上、明確に禁止する規定はありません。しかし、取引の実態がなく、単なる租税回避行為と税務署に判断された場合、損失の計上が否認されるリスクはゼロではありません。より安全を期すなら、売却から数日〜1週間程度時間を空ける、または別の銘柄に投資するといった対策が考えられます。
家族の名義で口座を作って取引し、利益を分散させるのは節税になりますか?
その方法は絶対に避けるべきです。取引資金の拠出者や、実際の取引判断をしているのがあなた自身である場合、それは単なる名義貸しとみなされます。その結果、利益はすべてあなたの所得として合算されるだけでなく、家族への資金移動が「贈与」と認定され、高額な贈与税が課される可能性があります。リスクが非常に高いので、絶対に行わないでください。
■ 「バレない」は命取り。無申告の重いペナルティ
「少額だから大丈夫」「海外の取引所だから追跡できない」といった考えは極めて危険です。税務当局は、国税総合管理(KSK)システムや、法律に基づく金融機関への「情報提供要請」、さらにはCRS(共通報告基準)に基づく国家間の情報交換を通じて、国内外の取引記録を把握する能力を持っています。
万が一、申告漏れが発覚した場合、本来納めるべき税金に加え、重いペナルティが課されます。具体的には、「無申告加算税(最大20%)」、意図的な隠蔽と判断された場合の「重加算税(40%)」、そして納税が遅れた日数に応じて課される利息にあたる「延滞税(年率最大14.6%)」です。正しい知識を持ち、誠実な申告をすることが、結果的にご自身の資産を守ることに繋がります。
□ 損益の正確な把握:損益計算ツールを使い、現時点での年間利益と含み損益を正確に把握する。 □ 損出し戦略の立案・実行:含み損のポジションをリスト化し、利益と相殺するための売却を検討・実行する。 □ 必要経費の集計と証拠保全:今年支払った経費の領収書や明細を集め、漏れなくリストアップする。 □ 所得控除の確認:iDeCoやふるさと納税の証明書など、申告に必要な書類を準備する。 □【高所得者向け】法人化の検討:信頼できる税理士を探し、相談のアポイントを取る。 □ 取引履歴のダウンロード:利用する全ての取引所・ウォレットから、年間取引履歴(CSV等)をダウンロードし、安全な場所に保管する。
💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
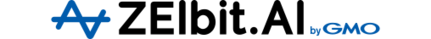
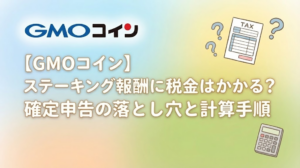


コメント 0件