【2025年最新】仮想通貨の経費はどこまで?PC・家賃の家事按分からツール代まで、確定申告で認められる費用一覧
※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
最近、仮想通貨の取引で少し利益が出たんですが、来年の確定申告が不安で…。どこまで経費として計上できるのか、ルールが複雑でよくわからないんです。PC代や家賃も経費にできるって本当ですか?
とても良いご質問ですね。仮想通貨の経費計上は、多くの投資家の方が悩むポイントです。結論から言うと、PC代や家賃も一定の条件下で経費に計上可能ですが、誰でも無条件に認められるわけではありません。
実は、2022年から国税庁のルールが変わり、あなたの仮想通貨取引が「業務」と認められるかどうかで、経費にできる範囲が大きく変わるようになったんです。この記事で、その重要な違いから具体的な計上方法まで、分かりやすく徹底解説していきますね。
この記事の目次
■ なぜ仮想通貨の経費は複雑?知っておくべき「雑所得」の仕組み
仮想通貨の経費計上がなぜ分かりにくいのか、その根本的な原因は、日本の税制における仮想通貨の独特な位置づけにあります。
株式投資やFXの利益は、多くの場合「申告分離課税」として他の所得と分けて一律の税率で計算されるため、比較的シンプルです。 しかし、仮想通貨の利益は原則として「雑所得」に分類され、給与所得など他の所得と合算して税額が決まる「総合課税」の対象となります。
総合課税は、所得が多ければ多いほど税率が上がる「累進課税」(最大45%)が適用されるため、計上できる経費の額が納税額に直接大きく影響します。 これに住民税(約10%)が加わるため、最大で約55%もの税率になる可能性があるのです。 だからこそ、経費を正しく理解し、漏れなく計上することが非常に重要になります。
出典: 国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」■ 【重要】仮想通貨の経費範囲を決める「業務」か「それ以外」かの判断基準
ここがこの記事で最も重要なポイントです。国税庁は2022年(令和4年分)から、同じ雑所得でも以下の2つに明確に区分しました。 そして、どちらに該当するかで、経費にできる範囲が全く異なります。
- 業務に係る雑所得: 経費の範囲が広い。売上原価や直接的な費用に加え、販売費や一般管理費など、その所得を生み出す業務に関連する費用も経費にできます。
- その他の雑所得: 経費の範囲が非常に限定的。経費にできるのは、売却した仮想通貨の取得価額や、売却時に支払った手数料など、所得を得るために「直接要した費用」のみです。 PC代やセミナー代などの間接的な費用は認められにくい傾向にあります。
では、自分の所得がどちらに分類されるのでしょうか?国税庁は具体的な基準を示しています。
原則として、その年の前々年(2年前)の仮想通貨取引による収入金額が300万円を超える場合には、「業務に係る雑所得」として扱われます。 ここでいう「収入金額」とは、利益ではなく売却額の合計である点に注意が必要です。 300万円以下の場合や、単発的な取引しかしていない多くの個人投資家は「その他の雑所得」に該当する可能性が高いと考えられます。
つまり、「この費用は経費になる?」と考える前に、まず「自分の所得はどちらの雑所得?」を判断することが、正しい経費計上のスタートラインになるのです。
■ 【仮想通貨 経費の基本】全投資家が計上できる費用リスト
所得区分に関わらず、すべての投資家が必要経費として計上できる項目です。これらは確実に押さえましょう。
- 譲渡原価(取得価額): 売却した仮想通貨を取得するためにかかった費用です。 所得は「売却価額 – 譲渡原価 – その他の必要経費」で計算されます。 個人の場合、取得価額の計算方法は「総平均法」か「移動平均法」のどちらかを選択します(届出がなければ総平均法)。
- 各種手数料: 取引所などに支払った売買手数料、送金手数料、日本円の出金手数料などです。 少額でも積み重なると大きな金額になるため、漏れなく集計しましょう。
【重要注意点】仮想通貨を購入する際に支払った手数料は、その年の経費にはせず、その仮想通貨の「取得価額」に含めて計算します。 これにより将来の譲渡原価が増え、結果的に利益を圧縮する効果があります。

AIでかんたん確定申告
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する暗号資産のAI損益計算サービスです。安心・かんたん・使いやすいサービスで、毎年の申告をスムーズに。
公式サイトで詳しく見る■ 【仮想通貨 経費の応用】PC・家賃を経費にする「家事按分」とは?
取引に不可欠なPCやスマートフォン、インターネット代。これらはプライベートでも使用する場合が多いため、経費にするには「家事按分」という手続きが必要です。
家事按分とは、支出の中から仮想通貨取引のために使用した割合を合理的な基準で算出し、その部分だけを経費として計上することです。 「なんとなく50%」のような曖昧な主張は税務調査で否認されるリスクがあるため、客観的で合理的な根拠を示すことが絶対条件です。
- 時間基準の例(通信費): スマホの1日の総利用時間のうち、取引や情報収集アプリの使用時間が平均4時間であれば、「4時間 ÷ 24時間 ≒ 16.7%」を業務割合として通信費に乗じます。 スクリーンタイムの記録などが証拠になります。
- 面積基準の例(家賃): 自宅全体の面積が70㎡で、そのうち取引専用で使う書斎が7㎡であれば、「7㎡ ÷ 70㎡ = 10%」を業務割合として家賃に乗じます。 間取り図などが証拠になります。
さらに、10万円以上の備品には「減価償却」というルールが適用されます。
- 10万円未満の備品: 「消耗品費」として購入した年に全額を経費にできます。
- 10万円以上の備品: 「固定資産」となり、購入代金を法定耐用年数(例: PCは4年)にわたって分割して経費計上します。 例えば20万円のPCなら、毎年5万円ずつ4年間かけて経費化します(この5万円をさらに家事按分する必要があります)。
■ 【仮想通貨 経費の発展】セミナー代やツール利用料はどこまでOK?
知識の習得や業務効率化のための費用も経費にできる可能性がありますが、ここでも所得区分が重要になります。
- セミナー参加費・書籍代: 取引が「業務に係る雑所得」や「事業所得」と見なされる場合は、収益を得るための知識投資として経費計上しやすいです。 一方、「その他の雑所得」の場合は、売買に直接関連しないとして否認されるリスクがあります。
- 損益計算ツール・ボット利用料: 確定申告に必須の損益計算を効率化するツールの利用料は、収益活動に直接関連するため、経費として認められる可能性が非常に高いです。
- 税理士への相談・申告依頼費用: 仮想通貨の複雑な税務計算について税理士に支払った報酬も、必要経費として計上できます。
■ 【取引別】マイニング・DeFi・NFTで認められる仮想通貨の経費
新しい分野の取引は、収入のタイミングと経費の範囲がそれぞれ異なります。
- マイニング: 報酬の仮想通貨を取得した時点の時価が収入になります。 経費としては、マイニング機器の購入費(10万円以上は減価償却)、電気代、通信費などが認められます。
- ステーキング・レンディング: 報酬や利子を受け取った時点の時価が収入です。 物理的なコストがほとんどかからないため、経費にできるのはごくわずかな手数料程度です。 報酬の大部分が所得となるため、納税資金の準備が重要です。
- DeFi(分散型金融): スワップ(交換)や報酬受領時に所得が発生しますが、税務上の明確な指針はまだなく、計算も複雑です。 支払ったガス代(ネットワーク手数料)は経費になる可能性がありますが、専門家への相談を強く推奨します。
- NFT(非代替性トークン): 転売目的で購入したNFTの売却益は、原則として「譲渡所得」となり、最大50万円の特別控除が使えるメリットがあります。 経費はNFTの購入費用や売却手数料です。
■ 【節税戦略】仮想通貨は事業所得で経費計上すべき?法人化のメリット
仮想通貨取引の規模が大きくなると、「事業所得」としての申告や「法人化」が節税の選択肢になります。
「事業所得」として認められると(年間の収入金額300万円超かつ帳簿保存が原則)、青色申告特別控除(最大65万円)や、損失を他の所得と相殺できる「損益通算」、損失を3年間繰り越せる「繰越控除」など、税制上の大きなメリットがあります。
さらに利益が大きくなった場合(年間所得800万〜900万円超が目安)は「法人化」も考えられますが、メリット・デメリットの双方を慎重に検討する必要があります。
| 項目 | 個人(事業所得) | 法人 |
|---|---|---|
| 適用税率 | 累進課税(住民税含め最大約55%) | 法人税等(実効税率最大約34%) |
| 損失の繰越控除 | 3年間 | 10年間 |
| 経費の範囲 | 広い | さらに広い(役員報酬、退職金等) |
| 含み益への課税 | なし | あり(期末時価評価) |
| 事務・コスト負担 | 高い(複式簿記) | 非常に高い(法人決算、社会保険等) |
法人化の最大のメリットは税率の低さですが、最大のデメリットは、売却していなくても期末時点の含み益に課税されるリスクがある点です。 このリスクを許容できるかが大きな判断基準となります。
■ 仮想通貨の経費と税務調査:否認されないための証拠保存ガイド
国税庁は国内取引所から取引データを直接入手しており、税務調査は年々強化されています。 申告内容の正当性を証明するため、以下の書類は必ず整理・保存しましょう。
- 取引履歴: 国内取引所の「年間取引報告書」は必須です。 海外取引所の場合は、自身で取引履歴(CSVファイルなど)を定期的にダウンロードして保管する義務があります。
- 経費の証拠: 計上したすべての支出について、領収書、レシート、請求書、クレジットカード明細などを保存します。
- 計算根拠: 家事按分の計算メモや、損益計算に使用したExcelファイルなども重要な証拠資料です。
これらの書類の保存期間は、原則5年、青色申告の場合は7年です。 将来に備え、一律で7年間保存しておくと安心です。 また、電子データで受け取ったものは、原則として電子データのまま保存する必要があります(電子帳簿保存法)。
■ 仮想通貨の経費に関するよくある質問(Q&A)
仮想通貨の利益が年間20万円以下なら、確定申告しなくていいんですよね?
それは注意が必要です。給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員の方で、他に確定申告をする必要がない場合に限り、仮想通貨を含む給与以外の所得が20万円以下であれば申告は不要です。
しかし、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除(1年目)などで確定申告をする場合は、たとえ仮想通貨の利益が1円であっても、その金額を合わせて申告しなければなりません。 「20万円ルール」は万能ではないと覚えておいてください。
今年は損失が出てしまったのですが、何もしなくていいですか?
申告義務はありませんが、2つの点で申告を検討する価値があります。まず、もし他に副業の原稿料など別の「雑所得」があれば、仮想通貨の損失と相殺(内部通算)して全体の税金を減らせる可能性があります。
また、年末に含み益のある別の仮想通貨を売却して利益を確定させ、損失とぶつける「損益調整」を行えば、将来払うはずだった税金を節税できます。 損失が出た年も、戦略的に動くことが大切です。
海外取引所での取引なら、税務署にはバレないのでは…?
その考えは非常に危険です。国税庁は「共通報告基準(CRS)」という国際的な枠組みを通じて、海外の金融口座情報を自動的に入手しています。また、国内取引所への送金履歴などから、海外取引所の利用状況も把握可能です。 「バレないだろう」という安易な考えで申告を怠ると、後から重加算税(最大40%)などの重いペナルティを課されるリスクがあります。 必ず正しく申告しましょう。
【今日の気づき】仮想通貨の経費計上のまとめ
- ①所得区分の自己診断: まず自分の取引が「業務」か「それ以外」かを見極める。これが経費範囲の出発点。
- ②証拠の徹底収集: 「証拠なくして経費なし」。すべての取引履歴と領収書を7年間は保存する。
- ③ルールの正確な理解と適用: 家事按分は「合理的根拠」を、10万円以上の備品は「減価償却」を正しく行う。
- ④専門家への相談: DeFiやNFT、事業所得化など、判断に迷う点は自己判断せず、仮想通貨に詳しい税理士に相談することが、将来のリスクを回避する最善策です。
💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
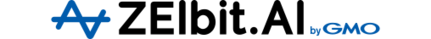
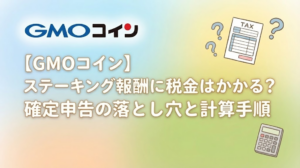


コメント 0件