【速報】金融庁、暗号資産税制を「分離課税」へ!税率55%→20%は実現するか?2026年度税制改正要望を徹底解説
※本記事は金融庁の公式資料「令和8(2026)年度税制改正要望について」に基づいて作成されています。
【速報】金融庁、2026年度税制改正で暗号資産の分離課税を要望!
2025年8月、金融庁は来年度(令和8年度・2026年度)の税制改正に向けた要望書を公表しました。その中で最も注目を集めているのが「暗号資産取引に係る課税の見直し」です。 これまで、暗号資産で得た利益は「雑所得」として扱われ、給与など他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象でした。これにより、所得が多い人ほど税率が上がり、住民税と合わせて最大55%もの高い税負担となる可能性がありました。
今回の要望は、この課税方式を、株式やFX(外国為替証拠金取引)などと同じ「申告分離課税」へと変更することを求めるものです。 もし実現すれば、暗号資産の利益は他の所得とは切り離して計算され、税率も一律になるため、多くの投資家にとって公平で分かりやすい税制へと変わる可能性があります。
この記事のポイント
税率55%→20%へ?現行の総合課税との違いを比較
「総合課税」から「申告分離課税」に変わると、具体的に何がどう変わるのでしょうか。株式投資などですでに適用されている制度を参考に、変更が実現した場合の主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 現行制度(総合課税) | 要望案(申告分離課税) |
|---|---|---|
| 税率 | 所得に応じて変動 (累進課税) 最大55% (所得税45% + 住民税10%) |
一律 合計20.315% (所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%) |
| 損益通算 | 暗号資産同士の利益と損失のみ通算可能。 給与所得や株式の損失とは通算できない。 |
上場株式等の他の金融商品の損益と通算できる可能性。 |
| 損失の繰越控除 | 損失を翌年以降に繰り越すことはできない。 | 損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の利益と相殺できる可能性。 |
このように、分離課税が導入されれば、税率が大幅に下がるだけでなく、年をまたいで損失を管理できる「繰越控除」が可能になるかもしれません。これにより、投資家はより長期的で戦略的な投資判断がしやすくなることが期待されます。
なぜ今?要望の背景と今後の展望
今回の要望の背景には、国内外で暗号資産への投資家が増加している現状があります。 政府が進める「資産運用立国」の実現に向け、国民が多様な金融商品へ投資しやすい環境を整えることが急務となっています。現状の複雑で高い税制は、日本の暗号資産市場の成長を妨げる一因と指摘されてきました。
また、金融庁は要望の中で、暗号資産ETF(上場投資信託)の組成についても税制面を含めて検討する必要があると言及しています。 これは、暗号資産を株式などと同等の「金融商品」として位置づけ、投資家保護のルールを整備していくという大きな流れの一環です。
- 投資家保護の法整備: 説明義務や適合性の原則など、株式と同等の規制を導入することが前提。
- 国際競争力の確保: 海外の主要国ではすでに分離課税が導入されており、グローバルな基準に合わせる狙い。
- 市場の健全な発展: 明確な税制は、新規参入者を増やし、市場全体の流動性と安定性の向上に繋がる。
残された課題:ウォレットや海外取引所の扱いは?
今回の金融庁の要望は大きな前進ですが、まだすべての論点がクリアになったわけではありません。特に、多くの投資家が利用している個人のウォレット(DeFiやNFT取引など)や、海外の暗号資産取引所を利用した場合の取り扱いについては、今回の要望書では具体的に触れられていません。
分離課税の対象となる取引の範囲が、国内の登録交換業者を通じたものに限定されるのか、それともより広範な取引を含むのかは、今後の議論の焦点となるでしょう。税務当局が取引内容を正確に把握するための報告義務の整備と併せて、慎重に検討が進められると考えられます。
よくある質問 (Q&A)
💡 今日の気づき
金融庁が暗号資産取引の「申告分離課税」化を正式に要望しました。実現すれば、税率は一律約20%となり、損失の繰越控除も可能になるかもしれません。ただし、これは投資家保護の法整備とセットで検討されるものであり、DeFiや海外取引所の扱いなど未確定な部分も多く残されています。この要望はまだ決定ではなく、年末の税制改正大綱で最終的な方向性が示されるため、今後の動向を注意深く見守る必要があります。
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
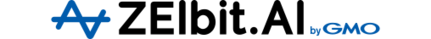



コメント 0件