仮想通貨の寄付と税金の罠|「みなし譲渡課税」と節税の完全ガイド【2025年最新】
※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
最近、応援したいプロジェクトに仮想通貨で寄付ができると聞きました。良いことだと思うのですが、税金ってどうなるんでしょうか?なんだか複雑そうで…。
素晴らしいご質問ですね。仮想通貨での寄付は社会貢献の新しい形として注目されていますが、おっしゃる通り、税金の仕組みは少し特殊です。知らずに進めると、善意の寄付が思わぬ税負担につながる可能性もあるんです。今回は、その複雑な税務ルールを、初心者の方にも分かりやすく完全ガイドします!
■ 仮想通貨の寄付で税金がかかる?基本の仕組み
まず押さえておきたいのは、個人が仮想通貨取引で得た利益の扱いです。株式投資の利益(譲渡所得)とは異なり、仮想通貨の利益は原則として「雑所得」に分類されます。 これは給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となり、所得税と住民税を合わせると最大で約55%の高い税率が課される可能性があります。
そして重要なのが、課税されるタイミングです。日本円に換金したときだけではありません。以下の行為も利益確定とみなされ、課税対象となります。
- ある仮想通貨を別の仮想通貨に交換した場合(例:BTC→ETH)
- 仮想通貨で商品やサービスを購入した場合
- そして、本記事のテーマである第三者(法人や団体)に仮想通貨を寄付した場合
価値が上がった仮想通貨をただ保有している状態(含み益)では、個人の場合、税金はかかりません。
■ 最大の壁「みなし譲渡所得課税」とは?
仮想通貨の寄付を考える上で、最も重要で、そして少し直感に反するルールが「みなし譲渡所得課税」です。これは、個人が法人や団体に資産(仮想通貨を含む)を無償で渡した(寄付した)場合、税法上、「その時点の時価で資産を売却(譲渡)したものとみなして」課税するという制度です。
つまり、善意で行った寄付にもかかわらず、取得した時からの値上がり益(含み益)が実現したものとして、その利益に対して所得税が課されてしまうのです。
この場合、あなたは仮想通貨を500万円で売却したと「みなされ」ます。
- みなし譲渡価額: 500万円
- 取得価額: 100万円
- 課税対象となる所得: 500万円 – 100万円 = 400万円

複雑な仮想通貨の税金計算、もう悩まない
ZEIbit.AIはGMOインターネットグループが提供する暗号資産のAI損益計算サービスです。複雑な計算も、取引履歴をアップロードするだけでカンタンに。安心・かんたん・使いやすいサービスで、毎年の申告をスムーズにしましょう。
公式サイトで詳しく見る■ 寄付で節税できる「寄付金控除」の活用法
もちろん、日本の税制も慈善活動を後押しする制度を用意しています。それが「寄付金控除」です。 国や地方公共団体、そして「認定NPO法人」などの適格な団体に寄付をすると、支払った税金の一部が戻ってくる仕組みです。
特に認定NPO法人などへの寄付では、以下の2つの控除方法から有利な方を選べます。
- 所得控除: 課税対象の所得から(寄付額 – 2,000円)を差し引く方法。所得税率が高い高所得者ほど節税効果が大きくなります。
- 税額控除: 計算された所得税額から直接(寄付額 – 2,000円)× 40%を差し引く方法。税額自体を減らすため、多くの場合で所得控除より有利になります。
しかし、ここに「寄付者のジレンマ」が生まれます。先ほどの例では、400万円の利益に対し最大180万円の税金(みなし譲渡課税)がかかる一方、500万円の寄付で受けられる税額控除は最大でも約200万円。慈善活動の結果、税金の支払が発生する可能性があるのです。これは、値上がりした資産の寄付でキャピタルゲイン税が免除される米国などの制度とは対照的です。
■ 【究極の節税策】租税特別措置法第40条(措法40条)とは?
このジレンマを根本的に解決する可能性を秘めた、非常に強力な制度があります。それが「租税特別措置法第40条(措法40条)」です。 これは、個人が含み益のある資産を国や認定NPO法人などの公益法人に寄付した場合、一定の要件を満たせば、「みなし譲渡所得税」が非課税になるという特例です。
この特例のすごい点は、税負担がゼロになるだけでなく、別途「寄付金控除」の適用も受けられることです。 つまり、税金を回避しつつ、さらに税の還付も受けられるという二重の恩恵があるのです。
| シナリオ | みなし譲渡所得税 (含み益400万円, 税率45%と仮定) |
寄付金控除による節税額 (税額控除40%) |
寄付者の純税務インパクト |
|---|---|---|---|
| 1. 通常の寄付 | -180万円(納税) | +1,999,200円 | +199,200円(便益) |
| 2. 措法40条の非課税特例を適用 | 0円(非課税) | +1,999,200円 | +1,999,200円(便益) |
この表を見れば、措法40条の威力が一目瞭然です。
■ 最大の論点:措法40条は仮想通貨に適用されるのか?
しかし、ここに最大のハードルがあります。法律が作られた当時には仮想通貨は存在せず、国税庁も仮想通貨が措法40条の対象になるかについて、明確な見解を示していないのが現状です。 これが、暗号資産寄付における最も重要かつ未解決の問題なのです。
適用をめぐる主な論点は以下の通りです。
- 「資産」の定義: 税法上、暗号資産は「資産」と扱われるため、対象となる可能性は十分にあります。 しかし、その新しさから当局が保守的な判断をするリスクも残ります。
- 「直接供する」要件: 寄付された資産が、NPOの「公益目的事業の用に直接供される」必要があります。 NPOが寄付された仮想通貨を即時に日本円に換金し、事業に使うのであれば要件を満たす可能性がありますが、保証はありません。
- 寄付者のリスク: 事前に国税庁へ申請し承認を得る必要がありますが、もし否認された場合、寄付者は遡って多額のみなし譲渡所得税を支払う義務を負うことになり、財務的リスクが非常に大きいのです。
結論として、措法40条は究極の節税策ですが、その適用は「ブラックボックス」の中です。実行には、暗号資産と資産寄付に精通した税理士への相談が絶対に不可欠です。
出典: 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」 出典: 内閣府NPOホームページ「現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充」なるほど…。措法40条はすごいけど、不確実なんですね。結局、仮想通貨で寄付するのはやめた方がいいんでしょうか?
いえ、必ずしもそうとは限りません。仕組みを理解し、正しい手順を踏むことが大切です。例えば、含み益が小さい場合や、寄付先のNPOが日本の税制に対応した「寄附金受領証明書」を発行できるかを確認するなど、注意すべき点があります。次に、よくある質問を見ていきましょう。
■ よくある質問(Q&A)
Q1: 寄付を受け取るNPO側には、どんな課題があるのですか?
A1: NPO側にも大きなハードルがあります。そもそもNPO名義で法人口座(ウォレット)を開設してくれる国内交換業者が少なかったり、価格変動リスクを管理する必要があったりします。 最も深刻なのは、寄付金控除に使える「寄附金受領証明書」を日本円建てで発行する体制が整っていない場合があることです。 海外プラットフォーム経由の寄付では、この証明書がもらえず、寄付者が控除を受けられないケースが多いので、事前の確認が必須です。
Q2: ふるさと納税のように、仮想通貨の利益で寄付上限額が上がったりしますか?
A2: その通りです!これは厳しい税制の中での光明と言えます。仮想通貨の利益を確定させると雑所得が増え、総所得金額が上がります。ふるさと納税の控除上限額は総所得金額に連動するため、結果的にふるさと納税で寄付できる枠が広がるというメリットがあります。 これは積極的なタックスプランニングとして活用できますね。
Q3: 今後、この複雑な税制は変わるのでしょうか?
A3: はい、その動きは活発化しています。業界団体からは、税率を株式などと同じ約20%の「申告分離課税」へ移行することや、損失を翌年に繰り越せる「繰越控除」の導入などが強く要望されています。 寄付税制の明確化も含まれており、2025年度の税制改正大綱でも「検討事項」として挙げられています。 まだ実現時期は未定ですが、より合理的で利用しやすい制度に変わっていくことが期待されています。
- 1. 「みなし譲渡課税」を忘れない:含み益のある仮想通貨の寄付は、その利益に課税されるのが大原則。手元にお金が入らなくても納税義務が発生します。
- 2. 「寄付金控除」と「領収書」を確認:認定NPO法人などへの寄付なら「税額控除」で税金を取り戻せる可能性があります。 ただし、控除には日本の税制で有効な「寄附金受領証明書」が必須です。寄付先に発行可能か必ず確認しましょう。
- 3. 究極の策「措法40条」は専門家と:みなし譲渡課税を非課税にできる強力な特例ですが、仮想通貨への適用は不透明でリスクを伴います。 検討する場合は、必ず暗号資産に詳しい税理士に相談してください。

この記事の監修者
村上 裕一(公認会計士・税理士)
公認会計士試験合格後、大手監査法人、メーカー経理財務、会計事務所を経て独立開業。仮想通貨・NFT・ブロックチェーンゲームを専門とする税理士として活躍。自らもSTEPNなどのブロックチェーンゲームなどをプレイし、多くの投資家の税務を支援している。
>> ホームページはこちら
💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
関連記事
- 当社は、提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その、適時性、適切性または完全性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
- 当社が提供するコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。
- 本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。当社も第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
- 本コンテンツから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから当社のウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社のウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
- 本コンテンツには作成者の分析及び意見が含まれる可能性がありますが、あくまでも作成者の見解であり、当社の見解ではありません。
以上
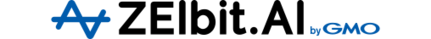
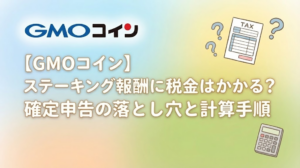


コメント 0件